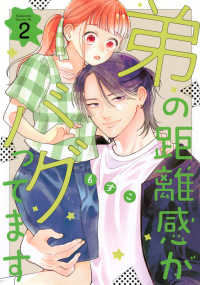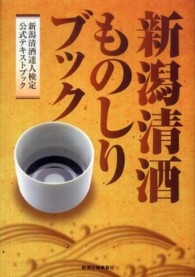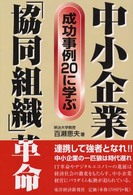出版社内容情報
神道は仏教をはじめ、各時代の様々な信仰や文化を取り込んで自らを形作ってきた。天照信仰、和歌・能などとの関わりから何が見えるか
内容説明
神道という言葉が信仰・宗教を指すようになるのは中世であり、仏教の一派ではない独立した神道流派は応仁期の吉田神道に始まる。神仏習合や密教、当時渡来した禅思想を基に続々と神道書が編まれ、神と仏を巡る多様な解釈が生み出された。『古今和歌集』注釈や能などの文芸世界とも相互作用を起こし、神道は豊穣な中世文化の一翼を担っていく。成立時から融通無碍に変化し続けた神道の本質とは何か。最新の研究からその姿に迫る。
目次
序章 中世神道の世界
第1章 中世神道の歴史
第2章 中世の神観念
附論1 漂着する土地・人―中世・近世神話における自国意識の屈折
第3章 中世の天照大神信仰―太陽神イメージの変容
第4章 空海と中世神道―両部神道との関わりを中心に
第5章 夢告と観想―僧たちの伊勢参宮
附論2 神祇信仰の場と「文」―中臣祓の変容
第6章 吉田兼倶の「神道」論
第7章 秘儀としての注釈
第8章 能と中世神道
著者等紹介
伊藤聡[イトウサトシ]
1961年、岐阜県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程満期退学(東洋哲学)。博士(文学)。現在、茨城大学人文社会科学部教授。専門は日本思想史。主な著書に『中世天照大神信仰の研究』(法藏館、2011年、第34回角川源義賞「歴史研究部門」)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
非実在の構想
Go Extreme
akuragitatata
maqiso
ちはなゆ
-
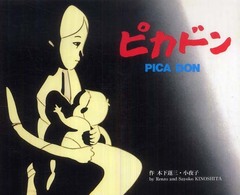
- 和書
- ピカドン (新装改訂版)