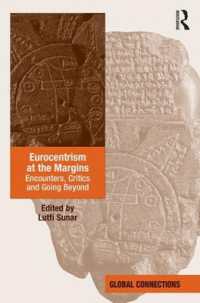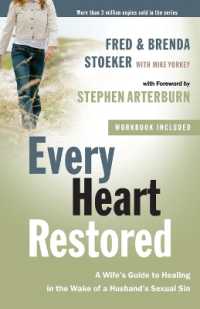出版社内容情報
不幸なことに、政治に〈嘘〉はつきものである。おそらくは世界中の政治に〈嘘〉が横行しているが、日本には日本独自の〈嘘〉が生まれる土壌があり、〈嘘〉の性格があり、その対処法と〈嘘〉があたかもないかのような振る舞い方がある。
なぜ日本では、グローバリゼーションで損をする人々の多数が、グローバリゼーションを推進する自民党を支持するのか。小選挙区制は日本に二大政党制を生むかに見えたが、なぜ一大与党と小野党が乱立する様相を呈しているのか――。本書は、こういった現代的な課題を、歴史から読み解くものである。
構成は、なぜ政治に嘘が生まれたかを中世の「職分」概念にさかのぼって考察する第Ⅰ部、生まれた嘘をどう対処するか、その原初のかたちを明治初期にみる第Ⅱ部、日本に特有ともいえる与党と支持基盤の違いのない野党がどう存続されたかを問う第Ⅲ部、日露戦争以来、現今の「地方創生」にいたるまで、国の財政が逼迫するたびに行われる、「希望」と引き替えに地域社会への献身が住民に要
求されるキャンペーンの構図を分析する第Ⅳ部からなる。
内容説明
政治に“嘘”がつきものなのはなぜか。絶対の権力というものがあるとすれば、嘘はいらない。それなりの反対勢力があるからこそ、それを迂回するために嘘が必要となり、反対する側も嘘を武器にするのだ。もちろん嘘には害があり、特に危険な嘘もある。世界中に嘘が横行する今、近現代の日本の経験は、嘘を減らし、嘘を生き延びるための教訓となるはずだ。複数政党政治が成立する条件と地域社会の未来像も、そこから見えてくる。
目次
1 “嘘”の起源―生真面目な社会(職分から政党への五〇〇年)
2 レトリックの効用―“嘘”の明治史(福地櫻痴の挑戦;循環の観念;五/七/五で嘘を切る)
3 野党 存続の条件(複数政党政治を支える嘘)
4 地方統治の作法(人類を鼓舞してきたもの;受益と負担の均衡を求めて―近現代日本の地域社会)
補章 一〇〇年後の日本―昆虫化日本 越冬始末
著者等紹介
五百旗頭薫[イオキベカオル]
1974年兵庫県生まれ。東京大学法学部卒業。同大学法学部助手、東京都立大学法学部助教授、東京大学社会科学研究所准教授などを経て、東京大学大学院法学政治学研究科教授。日本政治外交史専攻。博士(法学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
koji
politics
バルジ
cochou
spanasu
-

- 和書
- 劇場という名の星座