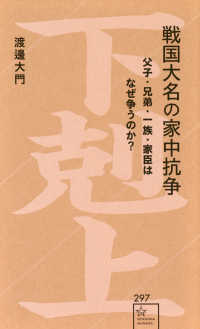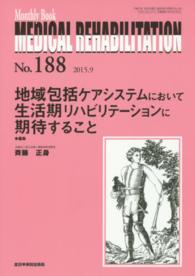出版社内容情報
泥沼化する日中戦争、太平洋を挟んだ日米戦争、東南アジアでの日英戦争、原爆投下、敗戦前後の日ソ戦争。
米中英ソとの複合戦争はいかに推移し、幾多の和平・収拾策にもかかわらず、なぜ早期に終戦できなかったか。
他方、本土決戦を目前に、なぜ「聖断」で終戦が可能となったか。
最新研究を踏まえ、昭和天皇・近衛文麿・木戸幸一・鈴木貫太郎らの肉声で辿り、第2次世界大戦の結末を巨細に描く。「狂気の時代」の真実に迫る。
【目次】
【目次】
まえがき
序 章 「複合戦争」の終わらせ方
「明るい戦争」 帝国陸海軍の作戦計画 「対米英蘭蒋作戦計画」と戦争終結構想 本書のねらい
第1章 太平洋戦線
陸海軍の戦略論争 ガダルカナル攻防戦 日独協力の対英戦略西アジア攻勢の政戦略 「絶対国防圏」――対米戦略の重視 サイパン殉国の歌――太平洋戦線の転機 「捷号」計画の破綻――フィリピンの放棄 沖縄から本土へ 長期消耗戦へ
第2章 大陸戦線
中国戦線の行き詰まり――重慶攻略の難題 「帝都空襲」の衝撃 「五号作戦」(四川進攻作戦)の挫折 重光の「和平構想」――「対支新政策」 「大東亜国際機構」構想 大東亜宣言と戦争目的の再定義 理念的アプローチの功罪 対中和平工作 「容共」政策への傾斜 繆斌工作の挫折 大陸戦線の結末――一号作戦の展開 インパール作戦 一号作戦と共産軍の成長 中国戦線の結末
第3章 徹底抗戦と徹底包囲
決号作戦計画――本土「最終決戦」 「天の利、人の和」――「国民総武装」の功罪 特攻と天皇 特攻の戦果 沖縄戦と戦艦大和特攻 大空襲の広がり 海上交通破壊の威力――機雷と艦砲射撃 ダウンフォール――オリンピック・コロネット作戦 南九州の防備 抗戦力の源泉
第4章 和平論のゆらぎ――小磯内閣の退陣
東條体制の崩壊とその後 三つの和平論 「近衛グループ」の和平構想 「真崎グループ」の即時和平論 「皇道派政権」構想の挫折 近衛拝謁の意味 近衛上奏と対米和平 グルー演説と上奏文の国際認識 近衛内閣案の挫折 高木惣吉の終戦研究近衛の米内留任論 木戸の「聖断」構想 小磯と「大本営内閣」案 小磯の辞意 米内の残留 小磯の「現役復帰」提案 小磯退陣と陸軍中堅層
第5章 鈴木内閣と終戦政略
鈴木首相の終戦指導 組閣と陸軍 米内留任と東郷の再入閣 陸軍中堅層の対応――「バドリオ」内閣? 本土決戦論 「決号」作戦計画と対ソ外交 六巨頭会談方式の確立 三つの対ソ交渉方針 「日ソ支」提携構想 広田・マリク会談 ソ連外交の「自立性」 鈴木の対米メッセージ 大東亜大使会議宣言の意味 戦争の争点を超えて 「無条件降伏」の拘束 ダレス工作とグルー声明 無条件降伏と国体問題 「平和の海」演説の波紋 非常時議会の意味 小野寺工作とヤルタ会談
第6章 「国策転換」の国内政治
近衛と米内の連携 六巨頭会談の硬直化と打開工作 高木の「研究対策」 阿南・米内会談の流産 六相懇談会 革新官僚グループの「本土徹底抗戦論」 「非常大権」発動論と議会 最後の「戦争指導大綱」 戦争目的としての「国体護持」と「皇土保全」 革新官僚の論理 木戸のイニシアティヴ
内容説明
泥沼化する日中戦争、太平洋を挟んだ日米戦争、東南アジアでの日英戦争、原爆投下、敗戦前後の日ソ戦争。米中英ソとの複合戦争はいかに推移し、幾多の和平・収拾策にもかかわらず、なぜ早期に終戦できなかったか。他方、本土決戦を目前に、なぜ「聖断」で終戦が可能となったか。最新研究を踏まえ、昭和天皇・近衛文麿・木戸幸一・鈴木貫太郎らの肉声で辿り、第2次世界大戦の結末を巨細に描く。「狂気の時代」の真実に迫る。
目次
序章 「複合戦争」の終わらせ方
第1章 太平洋戦線
第2章 大陸戦線
第3章 徹底抗戦と徹底包囲
第4章 和平論のゆらぎ―小磯内閣の退陣
第5章 鈴木内閣と終戦政略
第6章 「国策転換」の国内政治
第7章 近衛特使とポツダム宣言
第8章 二つの「外圧」と「聖断」
第9章 戦争終結
終章 敗戦の意味
著者等紹介
波多野澄雄[ハタノスミオ]
1947年岐阜県生まれ。72年慶應義塾大学法学部卒業。79年同大学院法学研究科博士課程修了、博士(法学)。防衛研修所戦史部勤務を経て、89年筑波大学社会科学系助教授。同教授、同人文社会科学研究科長、同副学長。現在、外務省「日本外交文書」編纂委員長、国立公文書館アジア歴史資料センター長。専攻・日本外交史。著書『幕僚たちの真珠湾』朝日選書、1991年/吉川弘文館、2013年。第21回吉田茂賞受賞。『太平洋戦争とアジア外交』東京大学出版会、1996年。第26回吉田茂賞受賞、など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
breguet4194q
skunk_c
ラウリスタ~
さとうしん
どら猫さとっち
-

- 電子書籍
- まとめ★グロッキーヘブン 分冊版(13)