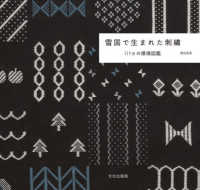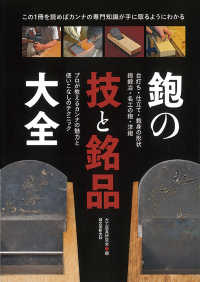出版社内容情報
父と子と聖霊は本質的に同一だという、初学者が誰しもつまずく教えについて専門家が丹念に解説。キリスト教の根本思想に迫る。
【目次】
内容説明
キリスト教の三位一体とは、父なる神、子なるイエス、聖霊の三者は本質的に同一だとする説である。ユダヤ教から分派したキリスト教が世界宗教へと発展を遂げる過程で、教会は神とイエスの関係の解釈に苦慮した。教会内の様々な派閥がしのぎを削った異端論争を経て、四世紀後半に三位一体の教義は確立を見る。初学者が誰しも躓く、この謎の多い教えについて、専門家が丹念に解説。キリスト教の根本思想に迫る。
目次
序章 キリスト教の成り立ち
第一章 三位一体の起源
第二章 キリストの神性をめぐる議論の始まり
第三章 異端論争の只中へ
第四章 教義理解の深まり
第五章 三位一体論教義の完成
第六章 西方ラテン世界における展開
終章 三位一体論の行方
著者等紹介
土橋茂樹[ツチハシシゲキ]
1953年(昭和28年)、東京都生まれ。上智大学大学院哲学研究科博士後期課程単位取得退学。上智大学哲学科助手、豪州カトリック大学・初期キリスト教研究所客員研究員、中央大学文学部教授などを経て、中央大学名誉教授。専門は古代中世哲学、教父学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
97
本書は、古代において三位一体の教義が確立するまでの経緯が、異端との論争や政治的な思惑などを含め詳しく紹介されている。最初は子の位置づけ、次に精霊の位置づけが議論の対象になり、「一つの本質存在、三つの位格(ペルソナ)」という教義に到達した歴史がとてもよくわかった。私は、三位一体の起源をギリシャ哲学に見出すという自由主義神学の考え方の影響を受けてきたが、一方、カール・バルト氏が、「神の自律的な自己啓示」として三位一体論を再解釈した歴史にも遭遇してきた。著者には、現代における三位一体論を是非著してほしいと願う。2026/01/29
Francis
18
キリスト教の根本である「三位一体」の教説がどのように確立したかを追った入門書。クリスチャンの私にも難しかったです。キリスト教と本当は合わないギリシャ哲学の考え方が入り込んできて議論が複雑化したことがうかがえる。初期のキリスト教会の公会議は東方教会の聖職者・神学者が大半で西方教会はほとんどいなかった、と言うのが結構衝撃的でした。しかしながらここで書かれた神学議論があったればこそキリスト教は宗教として確かなものになったのはまちがいない。日本でも「三位一体」と言う言葉が安易に使われていますが、やめて欲しいです。2025/09/10
うきこ
5
キリスト教における三位一体教義をその変遷を辿りながら歴史を追う本。 おそらくこれでも入門書に近い本なのだろうが、難解な哲学用語、似たような人名が散見されるので、初学者には苦しい難易度。でも読めなくはない。 意外だったのは三位一体がキリスト教が東西に分裂する前に確立。しかも論争の舞台となったのがほぼ東方だという点。西方の関わりは薄いらしい。それでも何故西方で受容され、今でも主要な祈りとしてミサで唱えられているのか。その点について本書では触れられていないので、今度はそちらを勉強したい。2025/09/09
みさと
4
聖書に直接三位一体に関する言及はない。一体どのような経緯で教会の正統教義となったのか。初代教会時代、哲学用語のギリシア語で神学が議論されていた。古代哲学は人間を超越したものを議論していたが、近代哲学は人間の理性を議論するように。当然神の位置づけが変化。では現代は?ニカイア公会議で三位一体の教えが確立したと思っていたがそんな簡単なものではなかった。また、神のみ力である聖霊を通して神のみ業とキリストが証しされると思っていたが、それはだいぶ新しい考えであることも。当たり前だと思っていたことと意味づけを問い直す。2025/11/04
ぴょライザーだぴょ
4
永遠の平和の根本問題を把握する良書ではあるが、信仰心を全面に出した書物であらねばならないと痛感する。『熱情ほとばしるイエスの叱責』や『パウロの奥義を語らせてくれという、熱い想い』などが前面に出てこないと、単なる歴史書扱いと成りかねない題材を扱っており、血の通っていない書物に堕する憂いを孕んでいる。ただ、世界メシア教をご存じの方にとっては、良書と成りうる。2025/10/04
-

- 和書
- ダリ