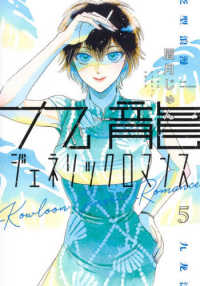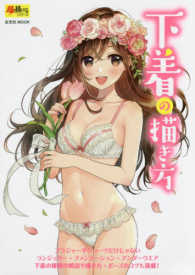出版社内容情報
史記、漢書、三国志、後漢書……元史、明史。中国では、前王朝の歴史を次の王朝が国家をあげて編纂することが多かった。これらは「正史」とされ、統べて二十四史と呼ぶ。中国史の根本史料でありここから歴史が記されてきた。
本書は、正史の起源から現代まで、各正史の特徴や意義、書史を追う。さらに、清史をめぐる中華民国と中華人民共和国の編纂の対立、元史の改定など、時の政治の影響を受けた問題なども記す。
内容説明
史記、漢書、三国志、後漢書…元史、明史。中国では、前王朝の歴史を次の王朝が国家をあげて編纂することが多かった。これらは「正史」とされ、統べて二十四史と呼ぶ。中国史の根本史料であり、ここから歴史が記されてきた。本書は、正史の起源から現代まで、各書の特徴や意義、歴史を追う。さらに、日本の史書との差異や、清史をめぐる中華民国と中華人民共和国の編纂方針の対立など、時の政治の影響を受けた問題を記す。
目次
序章 歴史と史学
第1章 前四史
第2章 唐の変容
第3章 正史の転換
第4章 「二十四史」の形成
第5章 「二十四史」の運命
終章 「正史」と日本人
著者等紹介
岡本隆司[オカモトタカシ]
1965(昭和40)年京都市生まれ。京都大学大学院文学研究科東洋史学博士後期課程満期退学。博士(文学)。宮崎大学助教授、京都府立大学教授を経て、2024年より早稲田大学教授。専攻は東洋史・近代アジア史。著書『近代中国と海関』(名古屋大学出版会、1999年。大平正芳記念賞受賞)『属国と自主のあいだ』(名古屋大学出版会、2004年。サントリー学芸賞受賞)『中国の誕生』(名古屋大学出版会、2017年。樫山純三賞、アジア太平洋賞特別賞受賞)ほか多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
サアベドラ
まえぞう
よっち
Toska
-

- 和書
- やってはいけない暗記術
-

- 洋書電子書籍
- Evolution of Govern…