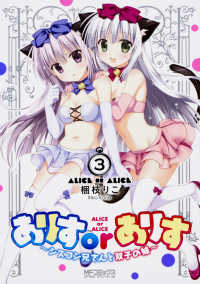出版社内容情報
米中の覇権争い、ウクライナや中東であいつぐ戦争。
試練の時代に、日本外交はどこへ、どう向かうべきか。
本書が探るのは戦争をせずに平和的に問題を解決するための要諦である。
現実主義と理想主義、戦略論と地政学などの諸理論や、E・H・カー、キッシンジャーらの分析に学び、陸奥、小村、幣原、吉田、安倍らの歩みから教訓を導く。
元外交官ならではの実践的な視点から、外交センスのある国をめざすための警鐘。
内容説明
米中の覇権争い、あいつぐ戦争。試練の時代に日本外交はどこへ、どう向かうべきか。本書が探るのは戦争をせず平和的に問題を解決するための要諦である。現実主義と理想主義、地政学と戦略論などの理論、E・H・カーやキッシンジャーらの分析に学ぶ。また陸奥宗光、小村寿太郎、幣原喜重郎、吉田茂、そして安倍晋三らの歩みから教訓を導く。元外交官の実践的な視点から、外交センスのある国に向けた指針を示す。
目次
序章 外交とは何か
第1章 日本外交史の光と影
第2章 戦前の教訓と戦後の展開
第3章 法と力
第4章 内政と外交
第5章 国益とパワー
第6章 戦略と地政学
第7章 外交力の要諦
終章 試練の日本外交
著者等紹介
小原雅博[コハラマサヒロ]
東京大学卒。1980年、外務省入省。2015年、東京大学大学院法学政治学研究科教授。21年より東京大学名誉教授。博士(国際関係学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぴー
68
外交に興味があるため購読。前半では明治〜太平洋戦争敗戦までの外交史を述べており、日本外交の失敗した理由をまとめている。それを踏まえ、中〜後半では外交にとって大切なポイントや考え方、現在の世界情勢をはじめ、日本が抱えている外交の課題等を指摘している。本書を通して、「外交」の難しさ、重要性を改めて実感した。特に、「最終章」の筆者の強いメッセージが印象に残る。近年、国際情勢は大きく変化しメディアでもよく取り上げられている。その際、私たちに短絡的に「外交」を捉えてはいけないと教えてくれる良書だったと思います。2025/04/05
nishiyan
14
元外交官の著者が日本外交史を読み解きながら、軍事と外交、内政と外交の在り方を論じた新書。本邦における外政家の代表として伊藤博文と吉田茂を挙げている点は興味深かった。幣原喜重郎に対する評価の厳しさについて気になったのだが、幣原が戦前の外相時代は外交官であり続けたことで、内政への関与を好まなかった点にあるのだろう。以前に読んだ別著者の本では首脳会談の危うさ、職業外交官の仕事が多岐にわたっていることを知ったが視点が変わると、こうも変わるものかと思った。外交は単独で語れるものではないということが最大の学びだろう。2025/06/21
とある本棚
13
刺さった一冊。元外交官出身で学者の著者が「外交」という概念と営みについて、歴史・理論・実践の各面に目配りしながら丁寧に纏めている。前半の日本外交の通史は簡潔ながら、類書と比べて外交官の役割に焦点を当てており参考になる。後半は地政学・内政との関係・国際法等てんこ盛りではあるが、内政との関係や外交実務の要諦(全体性・両立性・持続性・直接性・相互主義・合理性・正当性・戦略性)も興味深かった。著者の幣原・吉田評も面白かった。2025/09/28
クレイン
12
タイトル通り。歴史から遡って現代の問題点も検討している。個人的に思うが本書と考察であったりは別に外交にだけ当てはまるものではなく、普段の組織における所作にも役立つのではないだろうか。その観点で読んでいたので非常に勉強になった。2025/05/24
リットン
8
子供の頃から戦争は良くない、絶対にしてはならない、と刻まれて育つが、自分も含めて、当時の政府(もっというと暴走した軍部)が、悪かったのだろうという意識がある。けど、当時その潮流を生んだのは、社会のナショナリズムの高揚と国全体の過信にあったことを思うと、原因は一つではなく、複合的で、ダイナミズムの結果なのだろうと思う。そう思うと、今だってボタンの掛け違いでそういう流れになることはありうるということを忘れてはいけないなと思う。2025/06/20