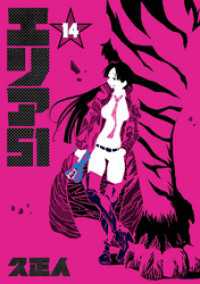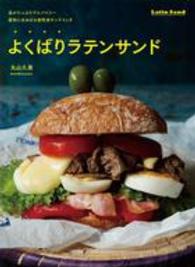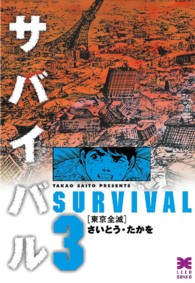出版社内容情報
明治の皇室典範制定で、なぜ皇位は男系男子に限られ、終戦後も維持されたのか。
皇室制度の専門家が、安定的皇位継承への道筋を探る。
内容説明
伊藤博文の主導で制定された明治の皇室典範。女帝・女系容認の可能性もあったが、皇位継承資格は「男系の男子」限定で、退位の規定もない。その骨格は戦後の皇室典範でも維持された。皇族男子の誕生は極めて稀で、皇族数の減少も続き、制度的矛盾が顕在化して久しい。小泉内閣時代に改正の検討が始まるも、進展はいまだ見えない。本格的議論の再開に向けて、皇室制度の専門家が論点を整理し、法改正への道筋を探る。
目次
第一章 明治皇室典範の起草をめぐる攻防(伊藤・シュタイン「邂逅」と柳原前光;伊藤の体制刷新と柳原の失速;高輪会議とは何だったのか;皇室典範の成立と保守派との攻防)
第二章 戦後の皇室典範制定(皇室の命運と知日派の台頭;占領統治と「国体護持」をめぐる攻防;現行皇室典範が抱えた矛盾―皇位継承と退位;狙われた皇室財産と皇籍離脱;矛盾が生んだ制度上の不具合)
第三章 顕在化した構造的矛盾(皇位継承問題とは何か;少子化と制度疲労;「生前退位」から典範改正へ)
第四章 象徴天皇制の新たな危機(戦後政治と昭和天皇;「象徴天皇」の模索;象徴天皇制と典範改正)
著者等紹介
笠原英彦[カサハラヒデヒコ]
1956年(昭和31年)、東京都に生まれる。1980年、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。1985年、同大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。法学博士。1988~89年、2000~01年、スタンフォード大学(米国)訪問研究員。慶應義塾大学法学部教授を経て、同大学名誉教授。専攻、日本政治史、日本行政史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
南北
ふたば
預かりマウス
Tomozuki Kibe