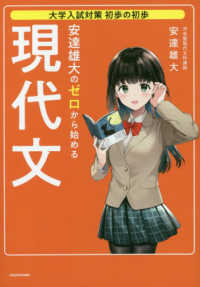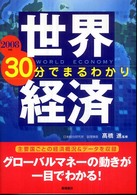出版社内容情報
平安遷都(794年)に始まる200年は激変の時代だった。律令国家は大きな政府から小さな政府へと変わり、豊かになった。その富はどこへ行ったのか? 奈良時代宮廷を支えた女官たちはどこへ行ったのか? 新しく生まれた摂関家とはなにか? 桓武天皇・在原業平・菅原道真・藤原基経らの超個性的メンバー、斎宮女御・中宮定子・紫式部ら綺羅星の女性たちが織り成すドラマとは? 「この国のかたち」を決めた平安前期のすべてが明かされる。
内容説明
平安遷都に始まる200年は激変の時代だった。律令国家は大きな政府から小さな政府へと変わったが、国家は豊かになった。その富はどこへ行ったのか。奈良時代の宮廷を支えた女官たちはどこへ行ったのか。新しく生まれた摂関家とは何か。桓武天皇、在原業平、菅原道真、藤原基経ら個性的メンバー、斎宮女御、中宮定子、紫式部ら綺羅星の如き女性が織り成すドラマとは?「この国のかたち」を決めた平安前期の全てが明かされる。
目次
はじめに―平安時代は一つの時代なのか?
序章 平安時代前期二〇〇年に何が起こったのか
第1章 すべては桓武天皇の行き当たりばっかりから始まった
第2章 貴族と文人はライバルだった
第3章 宮廷女性は政治の中心にいた
第4章 男性天皇の継承の始まりと「護送船団」の誕生
第5章 内親王が結婚できなくなった
第6章 斎宮・斎院・斎女は政治と切り離せない
第7章 文徳天皇という「時代」を考えた
第8章 紀貫之という男から平安文学が面白い理由を考えた
第9章 『源氏物語』の時代がやってきた
第10章 平安前期二〇〇年の行きついたところ
著者等紹介
榎村寛之[エムラヒロユキ]
1959年大阪府生まれ。大阪市立大学文学部卒業、岡山大学大学院文学研究科前期博士課程卒業、関西大学大学院文学研究科後期博士課程単位取得退学。三重県立斎宮歴史博物館学芸普及課長等を経て、現在、斎宮歴史博物館学芸員、関西大学等非常勤講師。専攻・日本古代史。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
六点
tamami
エドワード
ぽんすけ