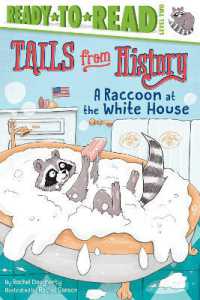出版社内容情報
絵に殉じたゴッホの筆遣い、色彩を見極めたセザンヌの眼、人間の生命を彫像にしたロダンの手。優れた絵画・彫刻は、作家の感性と知性が結晶した永遠の芸術である。東西の名品を堪能できる現場が美術館や展覧会だ。本書は、関心を開く・好きを見つける・読む・比べる・敷居をまたぐ・参加する・判るという7つの視点から、読者を現場にいざなう。80点のカラー図版とともに、美術体験の感動に迫り、愉しみ方を伝授する。
内容説明
絵に殉じたゴッホの筆遣い、色彩を見極めたセザンヌの眼、人間の生命を彫像にしたロダンの手。優れた絵画・彫刻は、作家の感性と知性が結晶した永遠の芸術である。東西の名品を堪能できる現場が美術館や展覧会だ。本書は、関心を開く・好きを見つける・読む・比べる・敷居をまたぐ・参加する・判るという7つの視点から、読者を現場にいざなう。80点のカラー図版とともに、美術体験の感動に迫り、愉しみ方を伝授する。
目次
第1章 関心を開く
第2章 好きを見つける
第3章 読む
第4章 比べる
第5章 敷居をまたぐ
第6章 参加する
第7章 判る判らない
むすび
著者等紹介
山梨俊夫[ヤマナシトシオ]
1948年横浜市生まれ。東京大学文学部美学芸術学科卒業。神奈川県立近代美術館館長、国立国際美術館館長を経て、社団法人全国美術館会議事務局長。著書『絵画の身振り』(昭森社、1990年、第2回倫雅美術奨励賞/ブリュッケ、2018年)『風景画考1~3』(ブリュッケ、2016年、第67回芸術選奨文部科学大臣賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
まちゃ
HaruNuevo
Francis
武井 康則