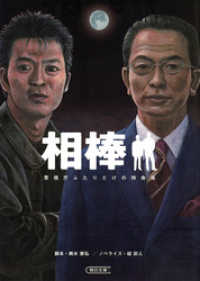出版社内容情報
生物の進化のメカニズムは、自然淘汰のなかで自らが生き残り、子孫を残して遺伝子をつなぐという「利己的」な動機に基づいて説明されることが多い。だとすれば、多くの種で観察される「利他的」な行動は、どのように説明すればよいのだろうか? 本書は、植物学者と動物学者がタッグを組み、その謎の答えに迫る。カギとなるのは「共生」という戦略である。互いの強みを融合し、欠点を補い合いながら自然淘汰に打ち克った生物たちのドラマをお届けする。
内容説明
生物の進化は、自らが生き残り、遺伝子を次世代に継承するための「利己的」なメカニズムとして説明されることが多い。だとすれば、種を超えて観察される「利他的」な行動は、どのように理解すればよいのだろうか?本書は、植物学者と動物学者がタッグを組み、その謎の答えに迫る。カギとなるのは「共生」という戦略である。互いの強みを融合し、欠点を補い合いながら自然淘汰に打ち克った生物たちのドラマ。
目次
序にかえて 生物は利己的か、利他的か
第1章 生命の特徴とは?
第2章 ミトコンドリアと葉緑体を飼いならす―細胞内共生説
第3章 共生のルーツは「盗っ人」だった?―盗葉緑体と盗毒
第4章 依存しきって生きるには―口を持たない深海動物の暮らし
第5章 昆虫と植物の華麗な騙し合い―Win‐Win関係の裏側
第6章 大事な共生相手を攻撃する理由―植物と菌のコミュニケーション
第7章 「超生命体」としての私たち―ヒトと腸内細菌の共生から考える
終章 進化と「利他」―生命のドライビング・フォース
著者等紹介
鈴木正彦[スズキマサヒコ]
1948年神奈川県生まれ。東京大学大学院理学系研究科植物学専攻博士課程修了。理学博士。三菱化成総合研究所・植物工学研究所チームリーダー、青森県農林水産部理事、農林総合研究センター・グリーンバイオセンター所長、北海道大学教授を歴任
末光〓志[スエミツタカシ]
1948年大阪府生まれ。東京大学大学院理学系研究科動物学専攻博士課程修了。理学博士。埼玉大学教授を経て、同名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
よっち
ひめぴょん
テツ
紡ぎ猫


![モーニング 2025年6号 [2025年1月9日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2005789.jpg)