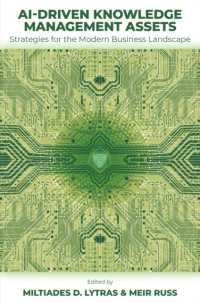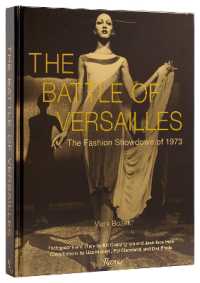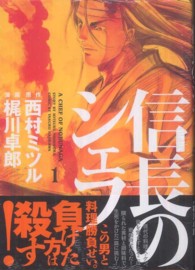出版社内容情報
21世紀に入った今でも世界は悲惨さに満ちている。飢餓、感染症、紛争などに留まらず、教育、児童労働、女性の社会参加、環境危機など、問題は枚挙にいとまがない。開発途上国への支援は、わたしたちにとって重要な使命である。一方で途上国自身にも、ITを用いた技術による生活水準の向上など、新たな動きが生まれつつある。当事者は何を求めているのか、どうすればそれを達成できるのか、効果的な支援とは何か――これらを解決しようと努めるのが、開発経済学である。その理論と現状を紹介し、国際協力のあり方、今こそ必要な理念について提言する。
内容説明
世界は今なお悲惨さに満ちている。飢餓、感染症、紛争にとどまらず、教育、児童労働、女性の社会参加、環境危機等、課題は山積みだ。途上国への支援は、私たちにとって重要な使命である。一方、途上国自身にも、新たな技術革新の動きが生じている。当事者は今、何を求め、それはどうすれば達成できるか?効果的な支援とは何か?開発経済学の理論と最新の動向を紹介し、国際協力のあり方や、今こそ必要な理念について提言する。
目次
第1章 開発経済学の始まりと終わり?(二重経済論―わたしと異なるあなた;植民地からの独立と経済成長―自分たちの国を興す ほか)
第2章 二一世紀の貧困―開発の成果と課題(世界の貧困の概観―数字に現れる貧困削減;不利な立場の人々―女性と性的少数者 ほか)
第3章 より豊かになるために―経済成長とイノベーションのメカニズム(経済成長の実績―アフリカの高成長国;経済成長のメカニズム―AKモデル ほか)
第4章 国際社会と開発途上国―援助と国際目標(政府開発援助―原型と展開;援助を有効に用いるために ほか)
著者等紹介
山形辰史[ヤマガタタツフミ]
1963年、岩手県生まれ。1986年、慶應義塾大学経済学部卒業。2000年、米国ロチェスター大学より博士号(経済学)取得。日本貿易振興機構アジア経済研究所研究員などを経て、立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部教授。元・国際開発学会会長。専攻・開発経済学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とある本棚
sk
Sanchai
Tomozuki Kibe
Kooya
-
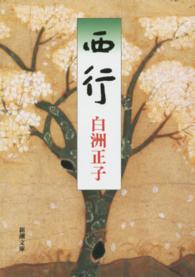
- 和書
- 西行 新潮文庫 (改版)