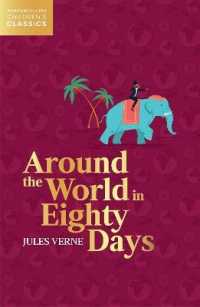出版社内容情報
小谷 賢[コタニケン]
著・文・その他
内容説明
国家の政策決定のために、情報分析や防諜活動を行うインテリジェンス。公安や外交、防衛を担う「国家の知性」である。戦後日本では、軍情報部の復活構想が潰えたのち、冷戦期に警察と内閣調査室を軸に再興。公安調査庁や自衛隊・外務省の情報機関と、共産主義陣営に相対した。冷戦後はより強力な組織を目指し、NSC(国家安全保障会議)創設に至る。CIA事案やソ連スパイ事件など豊富な事例を交え、戦後75年の秘史を描く。
目次
序章 インテリジェンスとは何か
第1章 占領期の組織再建
第2章 中央情報機構の創設
第3章 冷戦期の攻防
第4章 冷戦後のコミュニティの再編
第5章 第二次安倍政権時代の改革
終章 今後の課題
著者等紹介
小谷賢[コタニケン]
1973年京都府生まれ。立命館大学卒業、ロンドン大学キングス・カレッジ大学院修士課程修了。京都大学大学院博士課程修了。博士(人間・環境学)。英国王立統合軍防衛安保問題研究所(RUSI)客員研究員、防衛省防衛研究所戦史研究センター主任研究官、防衛大学校兼任講師などを経て、2016年より日本大学危機管理学部教授。著書『日本軍のインテリジェンス』(講談社選書メチエ、第16回山本七平賞奨励賞)ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
shincha
57
久しぶりに展開に身を任せ、ストーリーに埋もれながら楽しむ作品とは、真逆の一つ一つ頭の中で整理し、体系化しながら読まなければならない本を手に取った。ネガティブなイメージで刷り込まれていた諜報活動という言葉をインテリジェンスと言う言葉で表現し、認知させたのが佐藤優氏であったと知った。日本の縦割り行政の弊害と各省庁の利害が日本という国の利益に合致しない空恐ろしさを感じた。安倍元首相らの努力で内閣調査室が統合的に情報の管理と分析ができるようになったが、スパイ天国日本の現状は変わらない。国益の為に働く政治家を求む!2024/07/25
yamatoshiuruhashi
50
積読山よりやっと救出。戦前、山ほどあった〇〇機関についてはほとんど言及なく、敗戦後、冷戦期を乗り越え現在までの日本の情報機関、情報の扱い方について、どのような問題がありどのように対処してきたか。なかなか煩雑な人間、組織の関係を時勢、地勢など各種国際情勢を交えながらわかりやすく解き明かしていく名著である。内容については読友さんたちのレビューほど適切にまとめることができないので皆様にお任せ。ただ、未だにスパイ防止法すら成立させることができない政府にもそれを妨害する野党(どこの国のために働いている?)にも憤り。2024/05/13
Tomoichi
34
戦後新たに再建を目指したインテリジェンス機関の通史。吉田茂・町村・安倍と日本が普通の国になるために尽力した政治家をもっと評価してもいいと思う。しかしこういう機関の強化を邪魔する輩は、何かやましいことがあるんだろうね。ソ連(ロシア)の犬や中共・北朝鮮のポチ達。先日もあるコメンンテーターが平和国家日本って言ってたけど、ロシアも中共も北朝鮮もみんな平和国家って自分たちを思っているよ(笑)2024/03/10
鐵太郎
30
まず最初に、インテリジェンスとは情報のことを意味するが、機密や諜報の語感に近く、分析・評価された国家の政策決定や危機管理のための情報を意味する、と定義します。そして日本の戦中・戦後から始まるインテリジェンスの歴史をふり返り、インテリジェンスとは何か、どんな状況だったのか、どのように運営されていたのか、どうあるべきか、誰がどのように運用しようとしていたか、などを順番に整理して著述しています。第二次安倍内閣までなのですが、2022年以降どう日本が変わったのかを思うと感慨深いものがありますね。2024/10/09
とある本棚
30
インテリジェンスコミュニティの変遷を時系列で辿る一冊。ご多分に漏れずここでも役所間の縦割りが長らく課題となっており、その打破には2014年の国家安全保障局の設置を待たなければならなかった。日本でのスパイ事件も取り上げられているが、意外と政権の中枢にスパイが食い込んだ例もあり、日本の安全保障が不安になる。特定秘密保護法により、日本の秘密情報保持の体制が整い、米国をはじめ同盟国との機微な情報の共有も可能になったという指摘は目から鱗。特定秘密保護法は国外向けの要素が強かったことを初めて知った。2022/10/02