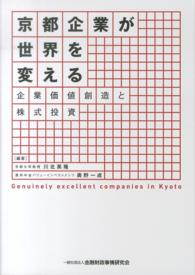出版社内容情報
農業経営と領地支配の仕組みとして、日本中世の政治・経済・社会の根幹をなした荘園制の全体像をわかりやすく解説する。
内容説明
荘園は日本の原風景である。公家や寺社、武家など支配層の私有農園をいい、奈良時代に始まる。平安後期から増大し、院政を行う上皇の権力の源となった。鎌倉時代以降、武士勢力に侵食されながらも存続し、応仁の乱後に終焉を迎えた。私利私欲で土地を囲い込み、国の秩序を乱したと見られがちな荘園だが、農業生産力向上や貨幣流通の進展に寄与した面は見逃せない。新知見もふまえ、中世社会の根幹だった荘園制の実像に迫る。
目次
第1章 律令制と初期荘園
第2章 摂関政治と免田型荘園
第3章 中世の胎動
第4章 院政と領域型荘園
第5章 武家政権と荘園制
第6章 中世荘園の世界
第7章 鎌倉後期の転換
第8章 南北朝・室町時代の荘園制
第9章 荘園制の動揺と解体
終章 日本の荘園とは何だったのか
著者等紹介
伊藤俊一[イトウトシカズ]
1958年(昭和33年)、愛知県に生まれる。京都大学文学部卒業。同大学大学院文学研究科に進み、博士(文学)を取得。名城大学教職課程部専任講師などを経て、同大学人間学部教授。専門分野は日本中世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
143
荘園とは律令制の公地公民を私利私欲で空文化したものと理解してきたが、上部構造たる朝廷や貴族、寺社の権力を経済的に支える下部構造として形成されたことがわかる。承久の乱以降に守護や地頭が設置され侵掠が進むと、権力までも武士たちに移行していく過程はマルクス経済学の見本のようだ。全国での実例を紹介しながら土地を奪う形で武士団が成立し、荘園の変質が日本史の変遷に直結したことを証明する。固有名詞や独自用語が頻出し理解が難しい部分もあるが、土地への執着や主従制の定着など日本人の心性成立にも及ぼした影響を考えさせられる。2021/12/02
遥かなる想い
131
2022年新書大賞第3位。 中世社会の根幹だった荘園制の実像に迫った本である。荘園の変遷という切り口で、日本史を 語った本書は 素人には新鮮で興味深い。 かつて学んだ日本史の教科書に出てきた 用語が懐かしく甦る。私利私欲で土地を 囲い込んだというイメージが強い荘園だが、 農業生産力向上などの貢献面もあることを 教えてくれる、そんな作品だった。 2022/04/01
六点
95
中卒以上の日本国民なら、誰もが耳の底に残る「墾田永年私財法」から始まり、戦国時代での廃絶に至るまで(東寺への最期の貢納は1574年!)、日本の古代から中世までの社会を、通奏低音の様に生き続けた、「荘園」についての長い物語である。長く続いた制度が、概ねそうであるように、時代や危機に追従して、形を変え、内実を変え続けた制度である。そうであったからこそ、超一流の専門家が大量の論文を書き、受験生の懊悩を弥増してきたのである。現在にも、地名や用水、祭祀施設などその痕跡は多く残っている。私達は歴史の中に生きているのだ2021/09/29
南北
89
奈良時代から室町時代までの荘園の歴史を概観した本。全体像がわかりやすく、新書らしい本だと思う。特筆すべきは当時の気温や降水量の推定値がグラフになっていることで、当時の収穫量が推測できるだけでなく、荘園の歴史とも深く関わりを持っている点を知ることができたのは収穫だった。われわれの祖先が戦乱や飢饉に対してどう対処してきたかがわかる好著だと思う。荘園の歴史を知りたいと思ったらこの本から取りかかることをお勧めする。2023/02/13
HANA
88
墾田永年私財法から室町末まで七百五十年、荘園の歴史を通史として描いた一冊。学校で習う荘園といえば墾田永年私財法と平安時代にちらと出てきただけでいつの間にか無くなっていたというイメージであるが、幾度の変遷を経てその内部にコスモロジーともいえるものを内包するようになっていたとは考えもしなかった。特に面白く読めたのは鎌倉時代における地頭の形成と室町の守護の形成、今までどこか腑に落ちなかった部分が紐解けていくような感じに襲われる。通史として読めるし、中央との関わりと荘園内部の世界観と至れり尽くせり。名著である。2021/10/30