出版社内容情報
歴史の教科書で最初に出てくる、旧石器・縄文・弥生・古墳時代。いわゆる「先史時代」である。明治から戦後にかけ定着していったこれらの時代区分だが、考古学の発展や新資料の発掘にともない、今も定説を覆す新発表が相次ぐ。本書では、その最前線を紹介。土器の誕生、人々の定住、土偶と祭祀、水田稲作の開始、「まち」の出現、古墳の成立――。時代が移り変わるプロセスを重視する「移行期」研究の視点から、「日本創世」の時代の実像を描き出す。
内容説明
日本史の教科書で最初に出てくる、旧石器・縄文・弥生・古墳時代。三万六〇〇〇年に及ぶ先史の時代区分は、明治から戦後にかけて定着していった。しかし近年、考古学の発展や新資料の発掘に伴い、それぞれの時代の捉え方は大きく塗りかえられている。本書では、各時代の「移行期」に焦点を当て、先史の実像を描き出す。人びとの定住、農耕の開始、祭祀、「都市」の出現、前方後円墳の成立―。研究の最前線を一望する決定版。
目次
序章 先史の時代区分―考古学ではこう考える(時代とは何か―Age/Era/Period;時代のはじまり―出現か、定着か ほか)
第1章 土器の定着、人びとの定住―旧石器時代から縄文時代へ(旧石器時代と気候変動―最終氷期から後氷期へ;土器の定着―指標1 縄文土器 ほか)
第2章 農耕社会の成立―縄文時代から弥生時代へ(弥生時代とは何か―画期をめぐる研究史;弥生式土器から水田稲作へ―弥生時代の指標の変化 ほか)
第3章 変化する社会と祭祀―弥生時代から古墳時代へ(流動化する人びと―気候変動の影響;「都市」の出現―纏向遺跡、比恵・那珂遺跡 ほか)
終章 先史時代を生きた人びとの文化―列島各地の暮らし(中の文化―アニミズムと穀霊;北の文化―「続縄文」の暮らし ほか)
著者等紹介
藤尾慎一郎[フジオシンイチロウ]
1959年、福岡市生まれ。広島大学文学部史学科卒業。九州大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。現在、国立歴史民俗博物館教授。専門は先史考古学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
やいっち
tamami
ひろし
loanmeadime
-

- 電子書籍
- MONOQLO 2025年8月号【電子…
-
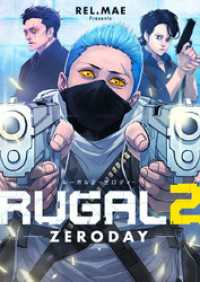
- 電子書籍
- ルーガル2 ーZERODAYー【タテヨ…
-
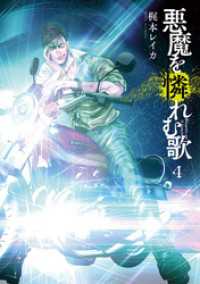
- 電子書籍
- 悪魔を憐れむ歌 4巻 バンチコミックス
-
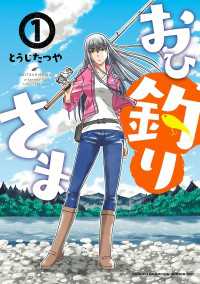
- 電子書籍
- おひ釣りさま 1 少年チャンピオンコミ…





