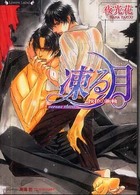出版社内容情報
明治維新は近代日本の原点とされる。だが、日本史上、これほど暗殺が頻発した時期はない。尊攘論の洗礼を受けた者たちはなぜ暗殺に走ったのか。大老井伊直弼暗殺から内務卿大久保利通に至る国家の首班、外国人、坂本龍馬なのど“志士”、さらには市井の人々が次々に標的となる…。事件のリアルな実相と世間の反応を描くとともに、後世、一方で暗殺者を顕彰し、もう一方で忌避した明治国家の対応を詳述。闇から見つめる幕末維新史。
内容説明
近代日本が生まれた幕末維新期。日本史上これほど暗殺が頻発した時期はない。尊皇攘夷論の洗礼を受けた者をはじめ、彼らはなぜ暗殺に走ったのか。大老井伊直弼から内務卿大久保利通に至る国家の中枢、外国人、坂本龍馬らの“志士”、市井の人々までが次々に標的となった事件の凄惨な実相と世間の反応を描く。さらに後世、一方で暗殺者を顕彰し、他方で忌避した明治国家の対応も詳述する。闇から見つめる幕末維新史。
目次
序章 繰り返されてきた暗殺
第1章 「夷狄」を排除する
第2章 「人斬り」往来
第3章 「言路洞開」を求めて
第4章 天皇権威の争奪戦
第5章 維新に乗り遅れた者たち
第6章 “正しい”暗殺、“正しくない”暗殺
終章 それでも続く暗殺
著者等紹介
一坂太郎[イチサカタロウ]
1966年兵庫県芦屋市生まれ。大正大学文学部史学科卒業。現在、萩博物館特別学芸員、防府天満宮歴史館顧問。春風文庫主宰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
79
政治体制への信頼が揺らぐ時、革命やクーデターの前に政権奪取を目指して暗殺事件が頻発するのは世界共通だ。ただ建前上は武家政権が続いていた日本では実力で敵を倒すのが当然視され、暗殺実行のハードルが低かったのは間違いない。今から振り返れば壮絶な暗黒史に思えるが、伊藤博文が暗殺関与を後悔しなかったように武士としては当然視されていたのか。テロの上に成立した近代日本の軍隊でも暗殺が肯定され、昭和軍部暴走の根源になったように思える。井伊直弼や大久保利通暗殺犯に対する大衆の同情は、226事件の青年将校への共感と共通する。2021/02/21
HANA
79
桜田門外の変から大久保利通暗殺まで、幕末から明治に至るまで起こった暗殺事件を記した一冊。考察とかは巻末にあるだけで、起こった事実を淡々と記しているように見えるんだけど、これが凄まじい。血風吹き荒れるというか、二、三頁に一人の割合で人が殺されていき、頁の合間から血が垂れてきそう。当時の暗殺横行が如何に凄まじかったかこれだけでわかるな。明治に入っての井伊直弼の変遷や明治元勲の暗殺に対する考え方等、事件以外でも教えられる事も多かった。現在との価値観の違いや「言路洞開」等、事件の列挙から見えてくるものも多い良書。2020/12/08
skunk_c
70
幕末京都の「天誅」と呼ばれるテロ・暗殺については、高校の歴史教科書では孝明天皇を悩ましたなんて書き方で済ませているが、それがいかなることだったかを具体的に書いた本は初めて読んだ。まるで暗殺データベースのような本だが、それなりに幕末史が見えてくる。当時の立場に立っての記述となっているのも歴史を知る上で良い(ちょっと口調が古くさいけど)。一方で「靖国合祀」や位階追贈が明治中期以降になっても、薩長中心の価値観で行われていたのがうかがわれ、初期明治政府の性格が出ている。しかし伊藤博文、若い頃はやんちゃだったのね。2021/01/21
Die-Go
59
図書館本。うひー、とにかく人が死にまくる。タイトルからして当たり前なんだけど、いささか食傷気味になってしまった。ただ、読んでいて感じたのは、暗殺でもなんでも、人殺しで英霊にはならないと言うこと。殺人は罪です。★★★☆☆2021/05/03
アイシャ
51
幕末から明治維新にかけての人物は実に大きな運命の波に飲まれ、その行く末はまったく予想のつかないものだったと思う。例えば新選組の斎藤一が明治時代を長く生き抜いたり、幕府軍として最後まで戦った榎本武揚が明治政府に要職を得たり。その逆に多くの優秀な人材が暗殺によって若い命を落としていった時代でもある。武市半平太の名前を見る頃には土佐、長州、薩摩が藩の存在をアピールするためにだけ暗殺が行われていたようだ。その残虐性も辟易する。明治時代になってからも暗殺は続き、大きな変革に置いて行かれた人々が多かったのだろう。2021/04/19