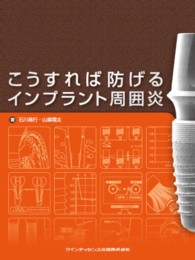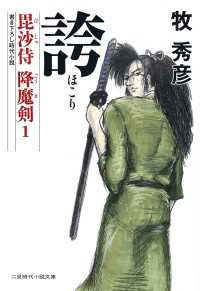出版社内容情報
新種発見! と聞くと滅多にない大ニュースとの印象を受けるが、地球上にはまだ数百万種以上もの未知種がいるとされ、誰もが新種に出会える可能性がある。本書は新種発見――生物(種)に新しい名前を与え、適切なカテゴリーに振り分ける――に日々取り組む動物分類学の入門書である。生物分類・命名法の基本から採集の楽しみ、論文発表の苦労と喜び、今後の動物分類学の可能性まで。生物の多様性とおもしろさを知る方法を伝授。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
COSMOS本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
90
現在、地球上で名前が付けられている生物は約180万種。だが、まだ数百万から数千万以上もの未知種が言われているそうだ。だから誰でも新種に出会う可能性がある、しかし新種としてそれを見つけただけでは新種にならない、ビデオで撮っても新種にならない。それが新種であることを証明しなければならない。その証明をするために膨大なデータや標本をもとに分類すること、それには採集も伴う。その定義や新種発見までの過程がわかりやすく書かれている。後半は命名やこれからの分類学について紹介されている。分類学、大変な学問ですね。図書館本2020/09/10
itokake
11
あこがれの職業、分類学者。その日々のお仕事を垣間見れた。1つの新種を記載(論文発表)するまで、約2年。数十年前、動物分類の門は28だったように記憶している。それが今では34とか。進歩が著しい。未記載種の推定が200万~1000万種という中、パソコンとネットを活用すれば人類が地球上の生命を全て記載する日はいずれ来るのだろうと希望が持てた。「名前がわかっている(海産)線虫を日本で見つけるのは宝くじを当てるようなもの」という言葉には驚いた。新種は、意外にも生活圏にいっぱいいるらしい。2022/08/25
bapaksejahtera
10
動物分類学を真正面から説いた入門書である。著者は海洋生物の専門なので例示する種は一様ではないが、学名の成り立ちや新種の発見と分類・命名法などおそらく初学者に向けて漏らすところはない。専門学者の熱意は伝わるが何とも地味な学問であり、事業仕分けなどでは苦労しそうな分野ではある。しかし著者の説く通り生物の多様性の維持は人間にとって極めて重要である。何しろ人間はまだ新生物を作り上げる事ができない。既存の材料から組立て直すことが精々なのだから。著者の熱い記述に促され半分義理と思い読み続けたのだが有益な読書であった。2020/12/28
(k・o・n)b
8
新種の「発見」を題材に分類学を一般向けに紹介する一冊。全ての生物学の基礎として、生物を体系づけ安定的に利用できるようにするため、既存の情報の整理から始めて、動物命名規約等のルールに則って命名を行う。確かに想像以上に地道で、ある意味「文系っぽい」。だが、生物自体について理解を深め、先人の積み重ねてきた分類体系の在り方を批判して、先に進めていく様は、まさしく「サイエンス」なのだろう。三崎の臨海実験所のエピソードが面白かった。油壺の海底にあんな奇妙奇天烈な生き物が生息していたとは…。2021/03/07
くまくま
7
新種を系統づける分類学。新種の発見というと深海やジャングルの奥地の探索というイメージだけど、新種として登録されるためには多くの時間がかかる地道な学問。あとがきの、新種は発見するのではなく、紹介(証明)して新種となる、というのは分類学者の仕事をよく表してる言葉だと思う。2021/01/30