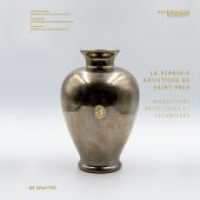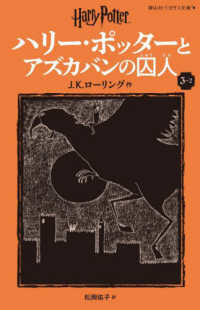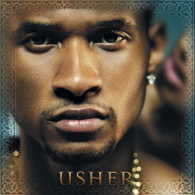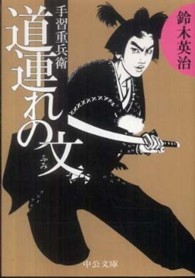出版社内容情報
科学のフロンティアである「意識」。そこでは、いかなる議論がなされているのか。本書は、意識の問題に取り組む研究者による最前線からのレポートだ。豊富な実験成果などを通して、人間の意識のかたちが見えてくるはずだ。
内容説明
物質と電気的・化学的反応の集合体にすぎない脳から、なぜ意識は生まれるのか―。多くの哲学者や科学者を悩ませた「意識」という謎。本書は、この不可思議な領域へ、クオリアやニューロンなどの知見を手がかりに迫る。さらには実験成果などを踏まえ、人工意識の可能性に切り込む。現代科学のホットトピックであり続ける意識研究の最前線から、気鋭の脳神経科学者が、人間と機械の関係が変わる未来を描きだす。
目次
第1章 意識の不思議
第2章 脳に意識の幻を追って
第3章 実験的意識研究の切り札 操作実験
第4章 意識の自然則とどう向き合うか
第5章 意識は情報か、アルゴリズムか
終章 脳の意識と機械の意識
著者等紹介
渡辺正峰[ワタナベマサタカ]
1970年千葉県生まれ。1993年東京大学工学部卒業、98年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。98年から2000年にかけて東京大学大学院工学系研究科助手、2000年から同助教授。カリフォルニア工科大学留学などを経て、東京大学大学院工学系研究科准教授およびドイツのマックス・プランク研究所客員研究員。専門は脳科学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
73
ひとは自己を完全に客観化できない、という人間の限界が理解できる。哲学と脳科学の親和性に思いを馳せると、文系と理系の区別が曖昧になっていくようで面白い。2018/04/24
honyomuhito
50
機械は意識を持つことができるのか。ブレードランナーや原作のアンドロイドは電気羊の夢を見るか?、マトリックス、ターミネーター、ロボコップ、銀河鉄道999、からくりサーカスもそうかな。SFじみたこの疑問をテーマにしたフィクションは、新旧含め枚挙にいとまがない。機械が意識を持てるのなら、将来的に機械に人間の一部を移植すれば、機械の中でヒトは第二の人生を送れるようになるのか。グーグルの技術開発部門を率いるレイ・カーツウェルはhttps://chirakattahondana.com/脳の意識-機械の意識/2018/06/17
Miyoshi Hirotaka
47
天満トビオは鉄腕アトムに、トチローはアルカイダ号のコンピュータに宿る魂になった。ドラえもんはのび太を助けるし、ターミネーターも二作目では機械という存在を超えた。漫画や映画の中では、意識の移植が確立し、機械の中で第二の人生を送ったり、機械が意識をもったりすることが可能。遅ればせながら科学者も漫画家や脚本家の後を追っている。但し、脳科学も一朝一夕にできたものではない。17世紀の「我思う、故に我あり」が起源。遠くを見渡すためには、巨人の肩に立つことが必要。人類史に輝くであろう大発明も先人の偉大な蓄積の先にある。2019/03/26
かごむし
30
テーマは意識。それは脳の働きそのものである。内容は難しい。著者の記述を見失わないように丁寧に読んだ。それまでの研究成果で明らかになったような事実についてはなんとかついていけたが、では、意識とはいったい何なのか、今後の研究課題、展望などに入っていくと、書かれていることを正しく理解できたか疑わしい。でも、わからないながら、意識というものの本質のおぼろげな輪郭や、ここまでわかっているのかという驚きがつまった一冊であった。こんな分野にもとっくに科学の光があたっていることを知り、難しい読書だったが得るものがあった。2020/08/07
那由田 忠
24
両眼視野闘争で、二図の真ん中に片方しか見えないのを(私は混じって見えるが)クオリア(感覚意識体験)なき視覚処理と説明する。しかし、真ん中の図はそうだが両端は見えるのでクオリアの一部に起こるだけ。元々脳が仮想現実をつくると考えれば、クオリアを「意識を持つものの特権」と言うのが変だし、意識の本質とまで言い切るのはいかがか。情報の中ではなくて神経のアルゴリズムに意識の座を見ようとするのはいいとしても、仮想現実がそのまま意識であるかのようなイケイケ説明は納得できない。「自由意志」の感覚こそ人間意識の本質と思う。2018/08/06