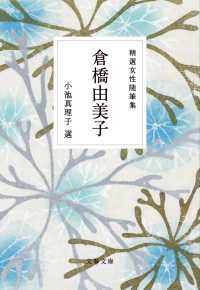内容説明
17世紀、王の絶対君主政への信奉は、清教徒・名誉革命を誘発し議会の権限が増す。18世紀半ば以降の産業革命下、内閣・政党が政治の主導権を獲得。グラッドストンら優れた政治家も現れ、19世紀、ヴィクトリア女王の時代は「世界の工場」かつ「最強国」となった。だが20世紀に入り、二つの世界大戦で国家は疲弊。経済停滞は「英国病」と揶揄された。本書は、近代化の胎動から、サッチャー、ブレアらが登場する現代までを描く。
目次
第7章 清教徒・名誉革命の時代―17世紀の変化
第8章 ハノーヴァー王朝下の議院内閣制確立―長い18世紀
第9章 イギリス帝国の黄金時代―19世紀の膨張
第10章 第一次世界大戦―いとこたちの戦争と貴族たちの黄昏
第11章 第二次世界大戦と帝国の溶解
第12章 エリザベス2世の時代―「英国病」からの蘇生
著者等紹介
君塚直隆[キミズカナオタカ]
1967年東京都生まれ。立教大学文学部史学科卒業。英国オックスフォード大学セント・アントニーズ・コレッジ留学。上智大学大学院文学研究科史学専攻博士後期課程修了。博士(史学)。東京大学客員助教授、神奈川県立外語短期大学教授などを経て、関東学院大学国際文化学部教授。専攻はイギリス政治外交史、ヨーロッパ国際政治史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
49
本当は世界史なんてものは無くて、本当は各国の歴史があるだけだという思いを強くしました。世界史はヘーゲル的な考察の方に任せるとして、簡単でもその国の歴史を概括しておくことに意味があると感じたのは、近代に入ると知らない固有名が結構あることでした。「日本史選択」の人は同じようなことに問題意識を感じている人は案外多いのではないかと思いますが、私の出した答えは「それぞれの国の歴史を簡単でもいいから通っておく」ことでした。この先も、固有名を求めて読んでいこうと思います。2021/07/12
skunk_c
43
下巻はいわゆるイギリス革命から現代まで。国王と議会の関係を軸に、諸王と代表的政治家を素描しながら、その展開を国際関係を交えて記述する。特に国王が外交に果たした役割の大きさについて知ることができたのが一番の収穫だった。経済や社会史はほぼ捨象されているが、これは著者自身が承知のこと。「あとがき」で『イギリス史10講』『イギリス近代史講義』という優れたものがあるからそちらを読んで欲しいと明記されており、偶然それらを読んでいたのでイギリス近代史の立体像が姿を現していくのを楽しむことができた。読み応えのある1冊。2019/06/15
まえぞう
31
こういう政治の話しが中心の歴史は最近のはやりではないのかもしれませんが、大きな流れを踏まえて次に進む時にはいいベースになるのではないかと思いました。2015/09/16
南北
30
ジェームズ1世から現代までのイギリスの歴史を「議会と王権」という切り口でまとめたものです。クロムウェルによる国王の処刑でイギリスの伝統は一時中断してしまいますが、やがて王政に戻っていきます。最近もEUからの要請もあって、ブレア首相(当時)が(あまり評判のよくない)貴族院の改革を行いましたが、議会の役割は時代によって変化しているものの、現在でもイギリスの政治には「王権と議会」とのバランスが重要であることがよくわかる本だと思います。2017/10/20
姉勤
29
イングランド王室を中心に、17世紀から近現代史まで。物語というか、あらすじなのは、新書の分量では致し方ないが、WW2戦後の政治史はわかりやすい。が、イギリスの未来にまで禍根を残した、世界史の肝と言える「三枚舌外交」、サイクス・ピコ協定に触れてないのは甚だ問題。別に英国人の国史の翻訳が読みたいわけではない。人種差別、金融操作、植民地政策、平和裡に世界帝国になったかのような不実な歴史勉強は、20世紀で終わりに。2016/08/01