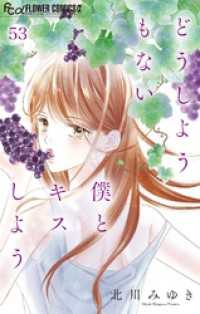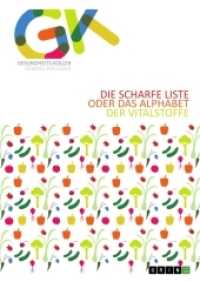内容説明
ビールやチョコレートなどで知られるベルギー。ヨーロッパの十字路に位置したため、古代から多くの戦乱の舞台となり、建国後もドイツやフランスなどの強国に翻弄されてきた。本書は、19世紀の建国時における混乱、植民地獲得、二つの世界大戦、フランス語とオランダ語という公用語をめぐる紛争、そして分裂危機までの道のりを描く。EU本部を首都に抱え、欧州の中心となったベルギーは、欧州の問題の縮図でもある。
目次
序章 ベルギー前史
第1章 ベルギー独立―一八三〇~六四年
第2章 帝国主義と民主主義―一八六五~一九〇九年
第3章 二つの大戦と国王問題―一九〇九~四四年
第4章 戦後復興期―一九四五~五九年
第5章 連邦国家への道―一九六〇~九二年
第6章 分裂危機―一九九三年~
終章 「合意の政治」のゆくえ
著者等紹介
松尾秀哉[マツオヒデヤ]
1965年生まれ。一橋大学社会学部卒業後、民間企業勤務を経て、2007年、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。聖学院大学政治経済学部准教授などを経て、14年より北海学園大学法学部教授。専門は比較政治、西欧政治史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
70
20世紀2回の大戦で蹂躙されたこの国は、フランス語を話すワロンと、オランダ語を話すフランデレン(言語的にはフラマンと言われることが多い)という二つの全く異なる社会からなっている。カトリック信仰がその紐帯になっている他、歴代の国王が国を束ねていくのにいろいろと苦心した話が興味深い。日本の天皇より遙かに政治的なのだ。ただし民主主義を理解し、議会や政治家との対話を欠かさない姿勢が、この国の王政を維持してきたと言える。特に近年の分離傾向(連邦化)を、国王が推進しつつ国家統一を保とうとする姿勢がよく理解できた。2022/03/12
molysk
64
フランス・ドイツ・イギリス・イタリアの4か国が交わる、ヨーロッパの十字路に位置するベルギーの歴史は、大国の思惑に翻弄されてきた。オランダからの独立、帝国主義競争、二度の世界大戦。また、ベルギーは言語問題を抱えた国家でもある。オランダ語を話すフランデレン地方と、フランス語を話すワロン地方は、対立を深めた末に連邦国家への道を歩んだ。これらの試練は、同時に「妥協の政治」「合意の政治」を育む土壌にもなった。戦後のベルギーは、欧州統合の旗を掲げる。欧州の対話の舞台となるEUの本部は、首都ブリュッセルに置かれる。2022/11/23
なかしー
37
再読。副題通りベルギーはヨーロッパの十字路(道路国家という揶揄も)であることが歴史背景からよく分かる一冊。1830年ネーデルランドから分離独立してからが本編なるがそれまでの時代も現代のフランデレンとワロンの言語問題(地域の区分なのに言語問題とはこれ如何に?って方と思った方は鋭い!!そこが2州を長年分かつ、原因となってます。)に結構影響していることが分かるので序章もしっかり読んでおきたい。約200年という歴史の浅い国ですがヨーロッパの複雑さ(宗教、言語、階級、地域、民族など)をギュッと詰まった国の物語です。2025/11/24
Tomoichi
27
英語公用語論や永世中立国化などを唱える人は是非この欧州の小国の歴史を学んで欲しい。ベルギーの歴史は列強の間で、ゲルマンとラテンの間で、翻弄された歴史である。繰り返されるフラマン語(オランダ語)地域とフランス語地域の対立、戦争の度に中立は無視され激戦地となりさらなる内部対立を生む。ドイツから来た王家は統一に尽力するが政治は安定せず。19歳から26歳まで過ごした私の第二の祖国の悲しみの物語。2016/11/05
健
17
正直、余り期待していなかったのだけどかなり面白かった。ベルギーは北半分がオランダ語圏で南半分がフランス語圏だけど、その起源がゲルマン民族の侵入に遡り、侵入を防いだ地域がフランス語圏として残ったとは驚きだった。1839年に独立して以来、言語問題で常に国が揺れているとのこと。それなら、フランスとオランダにそれぞれ併合すれば良いのにと思うんだけど、それを良しとしないのがベルギーらしく、揉める度に国王が仲裁に入って国の統一を維持しているようで、EUの本部がありながら、なんとも心もとない国の様子に悲哀を感じた。2022/08/19