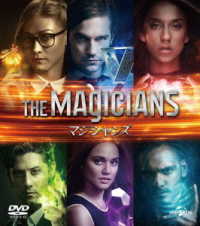内容説明
「非道の独裁者」―日本人の多くが抱くスターリンのイメージだろう。一九二〇年代末にソ連の指導的地位を固めて以降、農業集団化や大粛清により大量の死者を出し、晩年は猜疑心から側近を次々逮捕させた。だが、それでも彼を評価するロシア人が今なお多いのはなぜか。ソ連崩壊後の新史料をもとに、グルジアに生まれ、革命家として頭角を現し、最高指導者としてヒトラーやアメリカと渡りあった生涯をたどる。
目次
第1章 ゴリの少年
第2章 カフカースの革命家
第3章 コーバからスターリンへ
第4章 ロシアの革命と内戦
第5章 権力闘争の勝者
第6章 最高指導者
第7章 ヒトラーとの戦い
第8章 アメリカとの戦い
終章 歴史的評価をめぐって
著者等紹介
横手慎二[ヨコテシンジ]
1950(昭和25)年、東京都生まれ。東京大学教養学部卒業。同大学院博士課程中退。外務省調査員としてモスクワの日本大使館に勤務。慶應義塾大学法学部助教授を経て、同教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
307
謎につつまれたスターリンの生涯が判明可能な範囲で調査されていてよく分かった。著者はロシア関係では昔から第一人者だなと思った。2016/09/05
もりやまたけよし
56
スターリンの生きた時代のロシア通史として読みました。共産党が牛耳れば軍事国家になり、そのための工業化が進んで、犠牲になる人がいっぱい出るという感じですね。やっぱりそういう国はゴメンです。2021/01/31
Isamash
41
横手慎二・慶應大教授による2014年発行の著作。スターリンの一生の歩みを記述した著作で、歴史的評価におけるプラス面マイナス面で、プラス面を強調している様に思えた。まあスターリンが宗教学校出で、大学は出ていないものの幅広い範囲での読書家であったことは事実の様である。重工業を発展させたことが評価されていて、ロシア人の人気は高い様でもあるが、結局独ソ戦での勝利が彼の功績にされてる神話的な側面が強いとも思えた。不満としては、あれだけの規模の処刑を行えた非常さがどこから産まれてきたか、さっぱりと分からなかったこと。2022/04/07
Tomoichi
41
ソ連が崩壊し20年以上経ち、色々な資料も公開され、研究が進んだスターリンの実像。本書もイデオロギーから離れて無味無臭のスターリン像に迫っています。ただグルジアからどうボリシェヴィキの中で頭角を現していったかもう少し知りたかった。やっぱり分厚いスターリン伝を読まないとダメかな?2021/09/05
香取奈保佐
37
ロシア国民の少なからぬ人々が今もなおスターリンに愛着の気持ちを抱くのはなぜか。大粛清を断行した独裁者というイメージが先行するが、冷戦時代を終えたいま、改めて彼を評価しなおす必要がある。スターリンの生涯を追っていく本書は、ロシア革命・二つの世界大戦・冷戦初期を含む現代史の復習にも役立ち、中身のある内容だ。「すべての者は、ロシアが立ち遅れていたので、ロシアを打ち負かしたのである」。痛切な危機感を抱きながら大国を率いて激動の時代を生き抜いたのだ。簡単には評価できないのも当然かもしれない。あとで書評かきます。2014/10/11