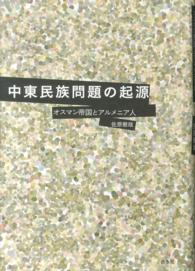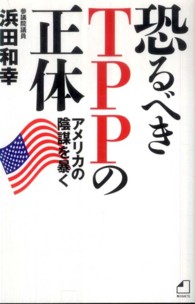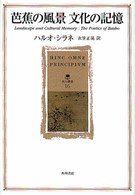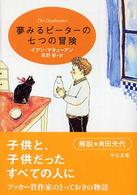内容説明
人は自分について否定的な言葉を聞きたくない。だが、悪いところを指摘する「ダメ出し」が相手に良い影響を与えることは、子どもの頃を思い返せば理解できるだろう。では、どうすれば反発やダメージを防ぎ、改善を促すことができるのか。本書は、上司と部下、友人、夫婦関係など様々な関係のなかで、その条件や活かし方などを豊富なデータから提示。相手にも、人間関係にも、イイ効果をもたらす「ダメ出し」の効用を説く。
目次
序章 ダメ出しとは何か
第1章 職場でいかに活かすか―どう言うべきか、どう聞くべきか
第2章 友人と知人、目上・対等・目下の人―関係性で何が違うのか
第3章 夫婦関係には何が起こるか―高め合い、それともけなし合い?
第4章 言う側と言われる側のズレ―誤解はどの程度生まれるのか
終章 力を引き出すには
著者等紹介
繁桝江里[シゲマスエリ]
1976年生まれ。99年早稲田大学第一文学部卒業。2005年東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得満期退学。博士(社会心理学)。山梨学院大学法学部政治行政学科講師、准教授を経て、青山学院大学教育心間科学部心理学科准教授。専攻、社会心理学、対人コミュニケーション(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
32
中根千枝のタテ社会の人間関係の現代版のような印象がある。職場の人間関係に悩む人には必要な本。ダメ出しはネガな結果をもたらすコミュニケーションではない(4頁)。専門用語ではダメ出しはネガティブ・フィードバックという(6頁)。意外にも、ダメ出しの頻度が高いことは、部下に悪影響をもたらさないという(55頁)のはイイ出しだけで人は伸びないことを示唆する。ダメ出しがパワハラにつながらぬ程度の匙加減が上司の手腕の見せ所だろう。ダメ出ししてよい職場環境は、目標がある組織。相互理解できる職場(71頁)。 2015/01/13
サアベドラ
7
「ダメ出しは良い効果をもたらすこともあります」という、いたって常識的なことを、多くの実験データを用いてくどくど説明した本。著者は社会心理学者で、本書は2003年に著者が発表した論文をもとに一般向けに手直ししたものらしい。心理学の研究手法に興味がある人には有用なのかもしれないが、実際に仕事場などでダメ出しの仕方・受け取り方に悩んでいる(本書を手に取る多くの人はこの動機だと思うが)人間にとっては、ところどころ役に立ちそうな情報はあるにせよ、全体として隔靴掻痒の感は否めなかった。2015/05/30
読書実践家
6
ダメ出しをうまく活かしていけるかどうかを検証している。人間関係や言い方が関与し、言われるが華ということも否めない。「素直さこそ最大の知性」という言葉を聞いたことがあるが、ダメ出しの時こそそれを発揮できるかどうかが重要だ。2016/04/02
おせきはん
4
社会心理学者が、実験データに基づきダメ出しを学術的に論じています。仕事で、上司として部下にダメ出しせざるを得ない状況が続く中、部下の反応に気になるところがあったため読みました。ダメ出しの効用も説明されていますが、ダメ出しをする側とされる側の人間関係が極めて重要であることがわかりました。部下個人ではなく仕事の内容そのものにダメ出ししており、個人的な感情を持ち込んでいないつもりであるだけでは不十分なので、有効なダメ出しの基盤となる信頼関係の強化を今まで以上に意識しようと思います。2014/07/12
amanon
3
基本的に否定的なイメージを持たれがちな「ダメ出し」という行為を掘り下げて論じるという趣旨には賛同できるのだけれど、いかんせんアンケートを主とした統計をベースにした分析というアプローチが個人的に馴染めない。こういうのは、大まかな傾向も勿論大事かもしれないが、個々のケースも交えながら論じていけば、一層説得力を持つのでは?と思えてならないのだが。後、ダメ出しという行為が意味を持つのは、親子、学校などの教育の現場が最たるものだと思うのだが、その点からの分析が殆どないのも残念。今度は別の方法での「ダメ出し」論を!2017/10/08