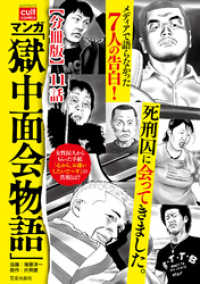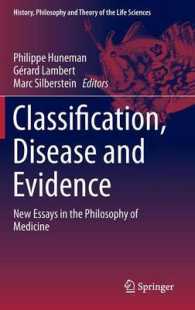内容説明
哲学とは何だろうか―。人間が世界と向き合い、自分の生の意味を顧みるとき、哲学は生まれた。古代から二一世紀の現代まで、人間は何を思考し、その精神の営為はどのような歴史を辿ってきたのだろうか。本書は、その歴史を「魂の哲学」から「意識の哲学」「言語の哲学」を経て、「生命の哲学」へと展開する一つのストーリーとして描く。ヘーゲル、シュペングラー、ローティの歴史哲学を超えた、新しい哲学史への招待。
目次
序章 哲学史のストーリー
第1章 魂の哲学―古代・中世(「魂」という原理;アテナイの哲学―プラトンとアリストテレス;地中海の哲学)
第2章 意識の哲学―近代(科学革命の時代―デカルトの登場;心身問題;経験論と超越論的観念論の立場)
第3章 言語の哲学―二〇世紀(論理学の革命;ケンブリッジから;アメリカへ)
第4章 生命の哲学―二一世紀へ向けて(生の哲学;ジェイムズとベルクソン;エコロジカルな心の哲学)
著者等紹介
伊藤邦武[イトウクニタケ]
1949(昭和24)年、神奈川県に生まれる。京都大学大学院博士課程修了。85年『パースのプラグマティズム』により文学博士。91年同大学文学部助教授。95年同大学大学院文学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう
44
哲学史をある程度概観した上で、各哲学者の書いたものを読んでみたいなと思って(超長期的展望です)まずは本書を読む。各論部分はざーっと目を通す感じの読み方になっちゃったけど(一つ一つを考えながら読む胆力がない)、デカルト とカントに割り当てられたページ数の多さから、彼らが準備した「近代」のインパクトの大きさ感じました。ベルクソンの時間と空間についての言説は、最近読んだ「春の雪」の一節を彷彿とさせ、ゾクゾクしちゃいました。こういう複数の本がリンクしてく感じって、これだけでとても楽しい。2022/09/24
佐島楓
31
デカルトの存在の意味、ラッセルとウィトゲンシュタインの関係など、よくわかっていなかったことがいくつか理解できた。物語とまではいかないが、ひとつの流れの中で哲学史を学べることは意義深く、折にふれ再読したい。2014/12/23
Tomoichi
24
哲学って一度はチャレンジしたいと思いつつ、頭が狂いそうなので、本書で御茶を濁す。数学と哲学との関係などは面白かったけど、数学が苦手なので、数学者も哲学者も理解できない。もっと気楽に生きていこうよ。2023/01/14
ゆう
21
2周目。第3章の解像度が少し上がった。第4章はほぼ文字を追っただけという感じ。3周目はノートとりながら読むかあ。2023/02/12
ほし
20
古代ギリシアからドゥルーズにいたるまで、哲学の歴史と変遷を追う一冊。入門書の類としてはかなり骨太でした。これを読むと、哲学というのは決して直線的に進化をしてきたようなものではなく、様々な放物線を描きながらも変化をしていくようなものであったことが伝わってきます。個々の哲学の解説だけではなく、それらがどのように関係しあってきたかも語られており、難しくも面白い一冊でした。2023/10/14