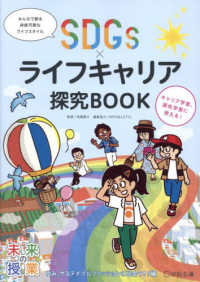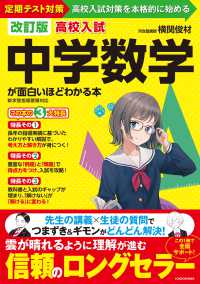内容説明
文明開化、関東大震災、空襲、高度成長…建設と破壊が何度も繰り返された東京だが、思わぬところに過去の記憶が残っている。日比谷公園の岩に刻まれた「不」の記号、神田三崎町に残る六叉路、明大前駅の陸橋下の謎のスペース、一列に並ぶ住宅など、興味深い構造物、地形を紹介し、その来歴を解説する。カラーで掲載した新旧の地図を見比べ、現地を歩いて発見すれば、土地の記憶が語りかけてくるだろう。
目次
1 石垣に刻まれた幻の水準点
2 明治の五公園は今
3 市営霊園の誕生と発展
4 都内に残る水道道路の謎
5 生まれた川と消えた村
6 幻の山手急行電鉄計画
7 軍都の面影を訪ねて
8 未完の帝都復興道路
9 廃線分譲地と過去の輪郭
著者等紹介
竹内正浩[タケウチマサヒロ]
1963年、愛知県生まれ。1985年、北海道大学卒業。JTBで20年近く旅行雑誌『旅』などの編集に携わり、各地を取材。退社後、地図や近代史研究をライフワークとするフリーライターに(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
57
10年前の本だが、面白かった。かなりミクロな部分にこだわっていて、最初はどうなるかと思ったけど、荒川放水路の章で完全に引き込まれた。首都高の5号線でよく近くを走ってるんだけど、こんな歴史があったんだとびっくり。地元近くもいくつか行ったことがあるけど、両国や小菅あたりをカメラを持ってうろつきたくなった。青山墓地界隈は何度か歩いたけど、その前に本書を読んでおけば良かったかな。掲載されている現状の地図が古くなっているけれど、日本地図センターの地理院地図で見れば新しいのがあるし。シリーズの他のも読まなきゃ!2021/03/31
saga
41
先に『都心の謎篇』を読んだが、本シリーズで総論とも言うべき本書をようやく読めた。読み始めればあっという間で、面白さの余韻が残る。几号水準点探しや五公園に出掛けたくなった。鉄道の話題も良かった。「未完の帝都復興道路」では、現代にこそ必要な都市計画道路ができる好機を逃し、後に日本橋や掘割の上に首都高速道路を建設しなければならない無様な姿をさらすに至った経緯を知り、何だか歯がゆい思いを抱いた。ブラタモリで紹介された場所が多く、これも読んでいて楽しめた要因だろう。2013/11/19
chanvesa
36
町田に実家があり、10年以上住んでいたのに、三多摩がなぜ東京都に編入されたのか、遅ればせながら知った。明治19年・青梅のコレラ騒動に対し、玉川上水から水を引くことから水源確保が目的(53、54頁)だという。また、「幻の山手急行電鉄計画」(91頁~)は興味深い。パンフレットのうたい文句に「山手急行は花柳電車なり」というのが入ってくるのが面白い。そもそも井の頭線に乗っていてクランクになっていることに気づかなかった。スマホのマップを見るくらいで、俯瞰的に地図を見ることが減った。視野も狭くなり、道も覚えられない。2018/01/29
金吾
25
東京は学生の時から身近な町であり結構フラフラしましたが、目的なく歩いている場合が多いため新鮮でした。偶然行ったことがある場所が出た時は少し嬉しかったです。古地図の記載がイメージアップに役立ち良かったです。参考にしながら散歩しようと思いました。2024/01/26
とみやん📖
22
タイトルと内容がきちんと一致するとても良い本。歴史とともに土地に改良というか、人為的な変更を加えられ、東京の土地利用も大きく変わっていくが、その片鱗を地図から読み解く。そんな作業の結晶。 公園、霊園、水道、鉄道など、当然ながらインフラに関わる歴史を追うことになる。特に首都東京は、国と都とプレーヤーが錯綜し、さらに複雑な関係をはらむ。そこが面白い。 個人的には、水道や貯水池、霊園について知識が乏しかったので楽しむことが出来た。洲崎、多磨霊園など、この本を手に出掛けたい。 2020/09/13
-

- 和書
- 自省録 大活字版岩波文庫