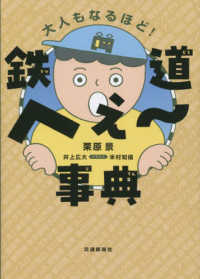出版社内容情報
戦後日本にとって「格差をなくす」とはこういうことだった──。
「全員が百点!」――戦後日本社会がつくりあげてきた特異な「平等」観。これを義務教育におけるお金の動きに焦点を合わせて解読する。
内容説明
戦後教育において「平等」はどのように考えられてきたのだろうか。本書が注目するのは、義務教育費の配分と日本的な平等主義のプロセスである。そのきわめて特異な背景には、戦前からの地方財政の逼迫と戦後の人口動態、アメリカから流入した「新教育」思想とが複雑に絡まり合っていた。セーフティネットとしての役割を維持してきたこの「戦後レジーム」がなぜ崩壊しつつあるのか、その原点を探る。
目次
プロローグ 平等神話の解読
第1章 対立の構図と問題の底流
第2章 戦前のトラウマと源流としてのアメリカ
第3章 設計図はいかに描かれたか
第4章 「面の平等」と知られざる革命
第5章 標準化のアンビバレンス
エピローグ 屈折する視線―個人と個性の錯視
著者等紹介
苅谷剛彦[カリヤタケヒコ]
1955年(昭和30年)、東京に生まれる。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了、ノースウェスタン大学大学院博士課程修了、Ph.D.(社会学)。放送教育開発センター助教授、東京大学大学院教育学研究科助教授、同大学院教授を経て、オックスフォード大学教授(2009年9月まで東京大学大学院教授を兼務)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かんがく
11
公的文書の引用とデータ分析が続く硬質な研究書で正直読みづらくて難しいが、教育問題をわかりやすい批判の的にしようとする世間の風潮へのアンチテーゼとしては有効だと思う。2023/05/09
isao_key
11
日本の学校教育の理想とは、授業のやり方や教育の内容次第では「全員が百点」をとれることが正しい教育だとされ、受け継がれてきた。本書は実際にその理想通り、学校は機能してきたか、地域での格差はどうであったかを解明している。かつては僻地の生徒のテストの平均点は、全国平均に比べてかなり劣っていた。現在では財政的に豊かな県と、財政的に厳しい県とでの学力調査平均点の相関関係は、ほとんどないが生活保護世帯の比率が高い県ほどテストの点が低くなる傾向は相変わらずだという。所得格差と貧困児童をいかに救えるかが、今問われている。2017/04/15
kanaoka 58
3
ゆとり教育や個を伸ばす自由な教育など綺麗ごとの言説、国家統制、画一化教育、一元的な能力主義への無責任な批判が繰り広げられ、新しい教育方針などの試みも行われたが、背景にあるイデオロギー闘争、二項対立図式的な政治抗争について冷静に見つめ直すことができました。 教育の共通化・標準化と差異化・自由化というものは、根源的には平等と自由という緊張感のある関係性の中で成り立つものであり、アンビバレンスな関係である。を理解しなければならず、性急・狭窄・単純な解決策は基礎となる土台・システムも破壊してしまうことにつながる。2026/02/09
Lulo
2
主張が丁寧で、謙虚で、興味深く、わかりやすかった。 引用されていたデータ一つ一つが面白く、もっと丁寧に読み返してみたい気もする。圧倒的に高い識字率を誇る日本、個性のなさばかりが取り沙汰されがちだが、学習指導要領等が果たした成果は大きいと個人的に思う。どんなことを議論するにせよ、教育の話題になると、教育への過度な期待を感じるし、教育を評価するのは難しいなぁと思う。2019/08/11
もくそん元帥
2
『大衆教育社会のゆくえ』の続編。今までになかった切り口で現代の教育を論じている教育社会学の良書。2012/09/18
-
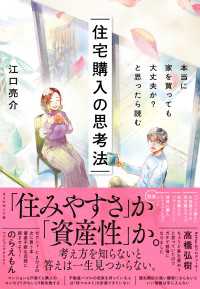
- 電子書籍
- 本当に家を買っても大丈夫か?と思ったら…
-
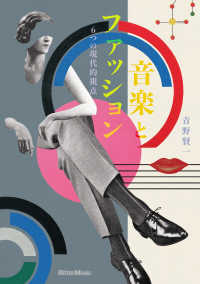
- 電子書籍
- 音楽とファッション 6つの現代的視点