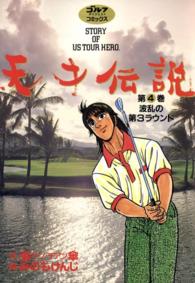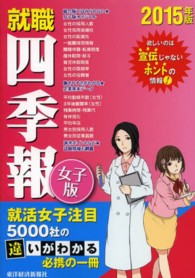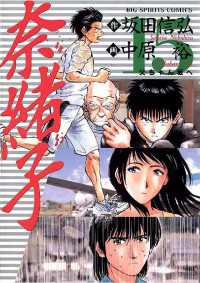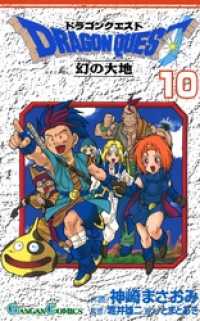内容説明
明治維新後、旧公卿・大名、維新功労者などから選ばれた華族。「皇族の藩屏」として、貴族院議員選出など多くの特権を享受した彼らは、近代日本の政治、経済、生活様式をリードした「恵まれた」階級のはずだった。日清・日露戦争後、膨大な軍人や財界人を組み込み拡大を続けたが、多様な出自ゆえ基盤は脆く、敗戦とともに消滅する。本書は、七八年間に一〇一一家存在したその実像を明らかにする。巻末に詳細な「華族一覧」付。
目次
序章 イメージとしての華族―鹿鳴館を彩った人びと
第1章 華族の成立
第2章 「選ばれた階級」の基盤構築
第3章 肥大化する華族―明治から大正へ
第4章 崩壊への道程―大正から昭和へ
終章 日本的「貴族」の終焉―敗戦・戦後
著者等紹介
小田部雄次[オタベユウジ]
1952(昭和27)年東京都生まれ。85年立教大学大学院文学研究科博士課程単位取得。立教大学非常勤講師などを経て、静岡福祉大学教授。専攻は日本近現代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おかむら
35
明治から終戦までの華族制度の通史。く、詳しい。戦前の皇族の結婚相手が華族だらけなので読んでみました。五摂家とかの公家、元大名、維新で功績あった藩士などが最初に華族となって、その後は軍人や財閥も。とんでもない大金持ち(ほぼ大名)くもいれば生活苦の人も。華族色々人生色々。でも英国の貴族と比べちゃうとなんかなー。ってダウントンアビーでしか知らんが。太宰治の「斜陽」を読み返したくなる。あと原節子の映画「安城家の舞踏会」も観たいわー。2017/04/13
rosetta
26
維新後日本の歴史に突如登場した華族と言う制度。江戸時代までの公家や大名、僧侶、神官から始まり維新の勲功者、後には臣籍降下の皇族や軍人や財閥も叙爵されるようになる。貴族院議員の大勢を占め(寧ろ華族以外にも勅選議員や高額納税者、学識者等が含まれていた事が意外だった)財産など特権的身分を有する階級。特に戦前は皇族と婚姻できるのは華族に限られていた事から美智子妃が如何に衝撃的存在だったことか。原敬も叙爵を打診されながら衆議院から貴族院に鞍替えされる事を嫌って断っていたとか、平民宰相のイメージも随分変わる。2020/04/04
浅香山三郎
11
日本の近代に、80年足らずの間存在した華族といふ身分について、その通史をおそらく初めて示したものではないか。いつ、だれが、なぜ華族となつたのかを順を追ひつつ示し、またその特権・醜聞、叙爵の基準と運用といつた点まで論点は多岐にわたる。 朝鮮貴族の叙爵、軍人に対する爵位の濫発などの様相については、本書により始めて知つた。帝国日本のありやうと連動し、社会の支配層を形成しつつも、やがて瓦解してゆく制度としての空虛さが、本書全体を通じてもよく伝はつてくる。2024/12/28
雲をみるひと
11
華族の成り立ちから終焉までの経緯、公家、武家、軍人、財界人、学者など華族の類型、貴族院議員や学習院入学などの華族特権など華族全般にくわしい。良本だと思う。華族が恣意的な階級だったことがよくわかる。2020/05/06
キョートマン
9
自分も華族みたいな高貴な生まれになりたかったなあ2020/07/31