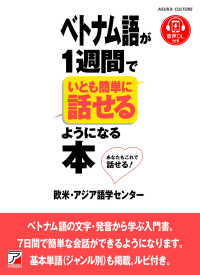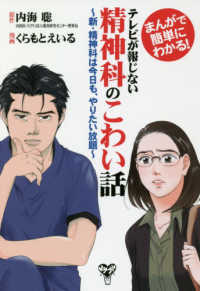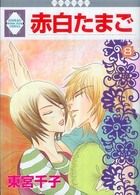出版社内容情報
戦後の市民による政治参加に圧倒的な支配力を及ぼした丸山眞男。そのカリスマ的な存在感の背景には、意外なことに、戦前、東大法学部の助手時代に体験した、右翼によるヒステリックな恫喝というトラウマがあった。本書は、六〇年安保を思想的に指導したものの、六〇年後半には学生から背を背けられる栄光と挫折の遍歴をたどり、丸山がその後のアカデミズムとジャーナリズムに与えた影響を検証する。
内容説明
戦後の市民による政治参加に圧倒的な支配力を及ぼした丸山眞男。そのカリスマ的な存在感の背景には、意外なことに、戦前、東大法学部の助手時代に体験した、右翼によるヒステリックな恫喝というトラウマがあった。本書は、六〇年安保を思想的に指導したものの、六〇年代後半には学生から一斉に背を向けられる栄光と挫折の遍歴をたどり、丸山がその後のアカデミズムとジャーナリズムに与えた影響を検証する。
目次
序章 輝ける知識人
1章 ある日の丸山眞男―帝大粛正学術講演会
2章 戦後啓蒙という大衆戦略
3章 絶妙なポジショニング
4章 大衆インテリの反逆
終章 大学・知識人・ジャーナリズム
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
99
丸山眞男についてどちらかというと、人物像やジャーナリスティックな観点から書かれています。苅部さんの書かれた岩波新書に比べるともう少し一般的な観点から書かれていてとっつきやすい気がします。ある意味丸山の生きた時代に彼の思想などがどのような影響を与えていったのかを時系列的に書かれているので、全体感を見るのにはいいのかもしれません。2024/08/05
HANA
71
進歩的知識人というと現在だと嘲弄の対象にしかならないけど、戦後一時期はそのスター性を発揮した時代があった。本書は丸山眞男を手掛かりにその時代を追った一冊。彼のトラウマとしての蓑田胸喜と大学粛正運動。学会とジャーナリズムの境界を上手く泳ぎ、最後は自分の育てようとした大衆インテリや学生運動に反逆されるというのは一編の物語を読んでるよう。現在はここでいう大衆インテリが国民総じてそうなり、学者の権威も落ちて久しい。そういう意味では共産主義と学者の権威がまだ輝きを保っていた時代に上手く乗れたという印象が残った。2023/03/21
寛生
34
丸山が受けた所謂〈トラウマ〉が彼の思想にどう影響したかということとあわせて、その時代に知識人達も社会と個人の間でどのようにもがき苦しんで考えていく道筋を一歩また一歩と進んでいったかという記述が印象的。後半、丸山をエリート知識人のようにして、彼の陰の部分の記述があるが、これは入門書(解説書)にはどうかと思う。入門書や解説書は、著者は出来る限り、言えばその思想家の亡霊に取り憑かれて、その思想の背後にある情熱ーそれは思想家のトラウマと切っても切れないものだろうがーに耳を傾けながらペンをとる覚悟が必要ではないか。2014/03/01
nbhd
19
ちょっと容易にはまとめられない超濃厚な一冊。資料引用の手捌きに、社会科学的分析の見事なこと、脳ミソ満腹の感。(1)丸山の心性の深みには、いつでも凶暴右翼・蓑田胸喜の影が…(2)敗戦直後しかり、安保闘争直後しかり共産党勢力が弱体化するとき、丸山は輝いた(3)実際の話、「超国家主義の論理と心理」は幅広い読者を得ていない(4)丸山の、実学と非実学、ジャーナリズムとアカデミズムのあいだの絶妙なポジショニング(5)丸山が育てた大衆インテリが、安保”敗退”の責任を丸山に当てつけるといった論理。超濃厚だから再読必至。2016/10/18
ヤギ郎
11
丸山眞男を主人公に,戦後日本の知識人や大学,ジャーナリズムの状況をつづった本。知的エリートと市民との差を埋めようと努力する人もいれば,自分が知的エリートであることを誇り(?)に思い他者を攻撃する人もいる。思想面について,戦前戦後を問わず,「この思想で行くぞ!」と特に宣言をした人がいるわけでもないのに,国全体が一つの思想へと傾いていく様子は不思議なものだ。また,肌で感じる社会の様子と実際に数字で見た時のギャップも驚きものだった。ちょっと古い本ではあるが,最終章は現代にも通ずることを書いていると思う。2018/01/09