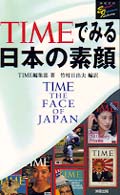出版社内容情報
神の庭から人間のにわへ、日本庭園の歴史と、植栽、石組、庭橋など作庭技術を詳細かつ平明に解説する。名園36景の見方、味わい方も紹介。
内容説明
石と水、そして木。日本庭園はこれらを美しく組み合わせ、その地の自然と歴史と文化を一体として表現した。方寸のなかに宇宙を展望しようとしたのである。その構成はどのようなものか、魅力はどこから生じるのか。神仏の庭、貴族の庭、大名庭園、庶民の庭を訪ねて考察する。また、植栽、石組、水工などの作庭技術を詳細に解説する。名庭名園三十六景の見方、味わい方も具体的に紹介する、本格的日本庭園入門書。
目次
プロローグ ホモ・ガーデエンシス(生き物とのふれあい「アメニティ・デザイン」;生きられる空間「ふるさとは守護霊」 ほか)
第1章 神仏の庭と人間のにわ(日本式庭園の時代と形式;飛鳥・奈良時代の庭園 ほか)
第2章 日本庭園の技術とこころ(日本式庭園の特色;植栽術―真副対・不等辺三角形 ほか)
第3章 日本の名園三十六景(毛越寺庭園(岩手県)
白水阿弥陀堂(福島県) ほか)
エピローグ ガーデニングからファーミングへ(ガーデンからランドスケープへ;これからは「ガーデニングからファーミングへ」)
著者等紹介
進士五十八[シンジイソヤ]
1944年(昭和9年)、京都市に生まれる。東京農業大学農学部造園学科卒業。農学博士。同大学教授、農学部長、地域環境科学部長を経て、1999年から6年間、学長を務める。その間、日本造園学会長、日本都市計画学会長、東南アジア国際農学会長。同大学教授、同大学院環境共生学専攻指導教授。このほか、政府の自然再生専門家会議、社会資本整備審議会委員。NPO法人の日本園芸福祉普及協会、美し国づくり協会の理事長、世田谷区教育委員などを兼ねる。日本造園学会賞、Golden Fortune賞、土木学会デザイン賞受賞。専攻、造園学、環境計画、景観政策
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
A.T
閑
chang_ume
moti moti
しゅう