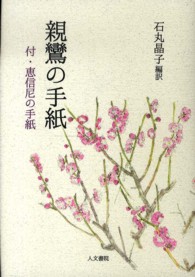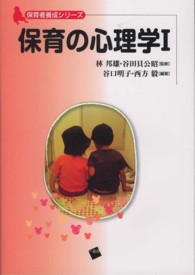出版社内容情報
捕虜処遇問題で悪化した英国との関係は好転し、ここにきて中国との関係はなぜ悪化したか。講和の歴史を辿り和解の可能性を探る。
内容説明
第二次世界大戦が終わり六〇年が過ぎ、戦争を直接記憶している人も少なくなった。だがいまだに戦争についての歴史認識をめぐり、近隣諸国との軋轢は絶えない。日本はいつ「戦争」の呪縛から解き放たれるのか―。一九九〇年代後半まで、日本軍による捕虜処遇問題で悪化していた英国との関係はなぜ好転し、ここにきて中国との関係はなぜ悪化したのか。講和の歴史を辿り、日英・日中の関係を比較し、和解の可能性を探る。
目次
序章 「戦後和解」とは何か
第1章 忘却から戦争犯罪裁判へ(神の前での講和;揺らぐ忘却―制裁の登場;勝者が敗者を裁く時代へ)
第2章 日本とドイツの異なる戦後(ドイツの選択;不完全だった東京裁判;曖昧化する日本の戦争責任)
第3章 英国との関係修復(日英関係に刺さった棘;さまざまな和解のかたち)
終章 日中和解の可能性
著者等紹介
小菅信子[コスゲノブコ]
1960(昭和35)年生まれ。上智大学文学部卒業。同大学院文学研究科史学専攻博士課程修了満期退学。ケンブリッジ大学国際研究センター客員研究員を経て、山梨学院大学法学部政治行政学科助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。