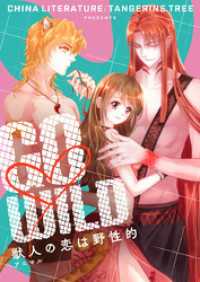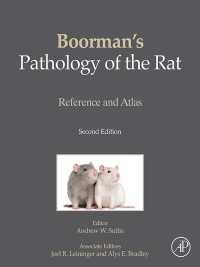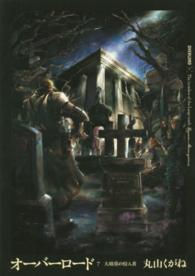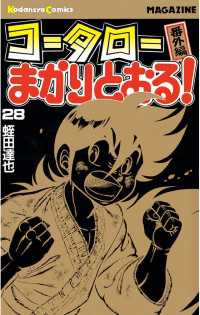内容説明
嘉永六年(一八五三)のペリー来航から明治二年(一八六九)の箱館五稜郭陥落までの幕末維新期、さまざまな国家構想が錯綜する中で政争や戦乱が展開された。こうした時代に生まれ、滅んだ新選組とは、どのような集団で、いかなる歴史的位置を占めていたのか。近藤勇らが幕末の京都で活躍できた政治的基盤や、近代性・合理性といった組織としての先駆的性格に着目しつつ、各種史料を丹念に検証する新選組全史。
目次
序章 新選組の時代
第1章 多摩と江戸
第2章 浪士組結成から池田屋事件へ
第3章 混迷する京都政局
第4章 江戸帰還後
第5章 会津・箱館戦争
終章 新選組の歴史的位置
著者等紹介
大石学[オオイシマナブ]
1953年(昭和28年)、東京都に生まれる。東京学芸大学卒業。同大学院修士課程修了。筑波大学大学院博士課程単位取得。徳川林政史研究所研究員、日本学術振興会奨励研究員、同特別研究員、名城大学助教授などを経て、現在、東京学芸大学教授。専攻、日本近世史
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ジュンジュン
14
新選組のイメージ~剣に生きた剣客集団、幕府に殉じた最後の武士~を刷新し、組織の実態を描く。他のレビュアーさんの「ラストサムライではなく、ファーストミリタリー」は、著書の主旨を見事に言い表していると思う。多くの犠牲を払いながらも、同志的結合から近代的な組織化へ、また、装備の西洋化も進める。それも新選組が特別だったわけではなく、所属する幕府軍全体の方針の一環として実施された。著者の主張は一貫していて分かりやすい。2021/09/05
ごん
10
意外と新選組に関するまとまった著作を読んだことがなかったので読んでしまいました。時代の流れのなかで生まれた新選組ですがあらゆる意味で封建制の枠から外れた組織だったようです。身分制や地域性の観点からも規格外ですし最後は刀から銃に武器を変えてしまいました。さて近藤も土方も幕末という動乱の時代に生まれてなかったら普通の市井の人で一生を終えたのでしょうね。まったく生まれ落ちる時代と場所は重要。短く雄々しく生きた彼らの人生は現代の我々にも心響くものがあります。ただその人生を真似するのは難しいのでしょうけど。2022/11/20
おMP夫人
10
中公新書らしい無難というか堅実なまとめられ具合に安心感を持つ本でした。英雄的に煽ることなく浪士組から函館戦争までの軌跡が淡々と紹介されています。そこに物足りなさを感じる人もいるでしょうが、初めて新選組に触れる人はもちろん、一通り関連書籍を手にした人がおさらいする時にもちょうど良い内容だと思います。特に目新しい記述はない本ですが、他の新選組本では扱いの大きくない幕府と多摩地域の関係にも多くのページが割かれているのは珍しいと思います。開府以来の密接な結びつきが近藤勇らの徳川への忠誠心の源流だと再確認しました。2013/01/21
いりあ
8
NHK大河ドラマ「新選組!」の時代考証を担当した大石学氏が新選組について解説した著作。1853年のペリー来航から1869年の箱館五稜郭陥落までの幕末維新期に活動した新選組を根拠となる各種文書を示し解説した著作。今なお多くの作品が取り上げ人気もある新選組は「最後の武士」というイメージが強い。しかし実際には官僚化、洋式軍備化を積極的に進めていた組織だったことが示されている。その弊害も出ていたようだが…。徳川幕府も時代遅れの組織ではなく、近代化を模索していた姿が見え、今後、新たな幕末の姿が描かれることに期待。2024/11/11
atlusbou
5
浪士組結成から箱館戦争で降伏するまでの流れを記載しています。様々な事件が起きますが、実際には6年間の出来事だと思うと、当時がどれだけ波乱の時代で明日生きられるかも分からない世だったかという事を感じました。京都にいる時は斬った斬られたのイメージする新選組でしたが、戊辰戦争では旧幕府軍の一部隊として銃や大砲を撃ち合う様を見て、筆者の言う様に近代化の流れも感じられました。2024/04/27