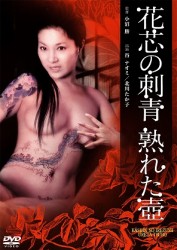内容説明
慶応四年春、幕府軍は鳥羽伏見の戦いで敗れて瓦解した。江戸城無血開城を経て戦場は東北に移る。長岡での激戦、白河の攻防、日光口での戦い…。会津藩をはじめ奥羽越列藩同盟軍は各地で戦いつづけるが、薩長軍はついに国境を破り会津若松に突入、一カ月に及ぶ篭城戦がはじまる。なぜこれほどまで戦わねばならなかったのか。会津藩の危機管理、軍事・外交、人材育成を検証しつつ、戊辰戦争最大の悲劇を浮き彫りにする。
目次
第1章 江戸の情勢(神保修理の死;容保の謝罪 ほか)
第2章 会津国境の戦争(越後方面の戦い;日光口の戦い ほか)
第3章 会津城下の戦い(敵、滝沢峠に迫る;老臣、家族の殉難 ほか)
第4章 篭城一か月(会津武士の意地;城外の戦い)
第5章 降参の白旗(米沢藩に工作を依頼;仰ぎ見る者なし)
著者等紹介
星亮一[ホシリョウイチ]
1935年(昭和10年)、仙台市に生まれる。東北大学文学部国史学科卒業、日本大学大学院総合社会情報研究科修了。作家・東北福祉大学兼任講師。著書に『奥羽越列藩同盟』(中公新書、1996年度福島民報出版文化賞)など
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
60
『奥羽越列藩同盟』より絞り込んだ内容でサクッと読了。史料の多くが口語訳されており、また豊富な図や写真もあって、著者本来の読みやすい文章のため、時を忘れて読み進んだ。しかし内容は重厚で、特に主役とも言うべき会津藩に対して容赦ない。戦略の欠如、準備不足などが敗因として捉えられており、それにより婦女、老人、幼子などに多くの犠牲が出たとする。一方城内外で闘った女性に対しては、山本八重子や山川操など高評価。一方薩長軍についても略奪や暴行を糾弾するなど、著者が「日本近代史の大汚点」とする戦争の悲惨さを描ききっている。2021/05/23
terve
32
白虎隊や娘子隊など悲劇として語られることの多い会津藩ですが、本書は会津藩がなぜ負けたのかを中心に語っています。藩として見通しの甘さとリスクマネジメントの拙さが大きな要因でしょう。特に、避難の鐘を鳴らしたのは敵軍が城下に侵入してからというように、あまりにも杜撰な対処をしており、戦時の残酷さとともに、上に立つものの判断の大切さを思い知らされます。新政府軍の恨みを一身に背負った会津藩ですが、もっと助かった命があると考えるとやりきれません。以前読んだ『特攻』『日本軍兵士』にも通じるものがあるかもしれません。2019/09/29
Isamash
26
仙台生まれ東北大国史学科卒作家の星亮一2003年発行書。会津で少年兵も参加の闘いがあったことは既知も、これ程に悲惨な戦争であったことは全く知らなかった。戦い前に家臣の婦女子が多く自死していたことには唖然。また籠城しての戦いに多くの婦人が男装して参加していたことにも。数百年前の戦争の記憶しか無いのに関わらず、武家の婦人たちが戦争に参加したり、子供達と心中するという精神に、教育の怖さを感じた。夫に生き残ることが大事と言われ必死に生き残った母と子供達の記録が救い。京都であれだけ名を挙げた会津藩の準備不備も意外。2024/05/13
はちこう
21
著者は、会津には「大村益次郎に匹敵するような戦略家が不在だった」と分析している。丁度「花神」読了後だったので考えさせられた。京都守護職の影響なのか、税制が過酷で周辺の住民たちから恨まれ積極的な協力が得られなかったことも会津の敗因だったようだ。本文中、占領軍による会津兵の遺体埋葬禁止令の記述があるが、最近の研究によると埋葬禁止令はなかったとのこと。後半、その遺体の埋葬に尽力した町野主水の名前が出てくる。会津に戦略家はいなかったかもしれないが、主水のような人格者がいたことは特筆に値すると思う。2023/08/07
ようはん
18
会津人にルーツを持つ自分だと会津藩にシンパシーを感じて本に書かれる会津戦争の悲惨さに目を背けたくなるが、会津藩の方も中通り方面等の近隣地域に掠奪を行い住民の恨みを買って新政府側に付かれた事が敗北の一要因であった事等、会津戦争における会津側の失敗や負の側面にも触れている。2020/07/23