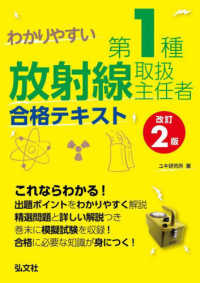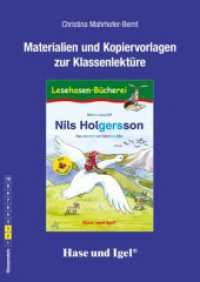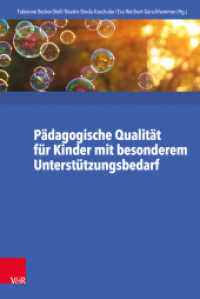内容説明
幕府歩兵隊をご存じだろうか。幕末の徳川幕府には近代装備の兵士がいた。水戸の天狗党とたたかい、長州の奇兵隊とたたかい、薩摩の小銃隊とたたかい、幕府瓦解の後は、関東・東北・北海道を転戦し、全官軍を向こうにまわして最終ラウンドを飾った。幕末の歩兵は、サムライでもなく帝国陸軍の兵隊でもなかった。この歩兵隊という特定の視界から幕府倒潰の秘密に迫る回路を探り、彼らを歴史の主役に抜擢する。
目次
第1章 幕府歩兵隊へのファン・レター
第2章 歩兵組の創設まで
第3章 歩兵の社会学
第4章 長州戦争と幕府歩兵隊
第5章 慶応の兵制改革
第6章 鳥羽伏見の戦
第7章 戊辰戦争と歩兵隊
著者等紹介
野口武彦[ノグチタケヒコ]
1937年(昭和12年)東京に生まれる。1962年、早稲田大学文学部卒業。その後、東京大学文学部に転じ、同大学院博士課程中退。神戸大学文学部教授を経て文芸評論家。主な著書に『江戸の歴史家』(筑摩書房、1979)(サントリー学芸賞)、『「源氏物語」を江戸から読む』(講談社、1985)(文部大臣賞)、『江戸の兵学思想』(中央公論社、1991)(和辻哲郎文化賞)など
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
65
幕末史を俯瞰しながら、語られるのは幕府が創設した銃を持つ歩兵軍団。当時の旗本およびその師弟たちは兵士としては使い物にならない者も多かったようで、幕末には江戸の下町に集まってきていた浮浪者や博徒などの荒くれ者を雇い兵として歩兵か、訓練を施したようだ。したがって素行は悪く駐屯地界隈では狼藉を働いたようだが、戦場では奇兵隊や薩摩軍に劣らぬ戦いをしたとか。著者はその場面を「活写」することで、この「戦うしか生きる術のない」プロレタリアート集団を描く。特に江戸開城後箱館戦争までのその戦いぶりがなかなかスリリング。2022/05/26
ホークス
33
2002年刊。幕末に作られた幕府直轄の歩兵隊について成立〜最期を検証。平民中心で、無職者や無法者が多く加わっていた。 長州に負けて刀槍の不利を悟り、遅まきながら銃にシフト。鳥羽伏見など戦闘の解説は歩兵隊目線で迫力がある。武器、訓練、衣装の話も面白い。以下は私の理解。⚫︎戦って勝つ前提条件は、苛烈なまでの目的意識。幕府は現状維持に適応しており、今さら戦時機能を取り戻せなかった。それぞれの空気で各々が動く⚫︎徳川慶喜は軍事的勝利への意思が薄く(難しいとは思うが)、武の総本家たる幕府の正統性喪失を体現していた。2025/08/16
印度 洋一郎
9
幕末に西洋文明と接触し、軍備の近代化に乗り出した徳川幕府の正に切り札的部隊だった「歩兵隊」。その誕生から、幕府を離脱して戊辰戦争を転戦した最期までを追った好著。とにかく文体が読み易く、テンポの良い語り口だ。江戸の喰いつめ者達が集まったやさぐれ集団ながらも、実戦で犠牲を出して、近代戦を体得していった。これはそのまま、封建時代の侍から、明治時代の日本軍への、正に過渡期に日本人がどうやって近代軍を受け入れていったか、その貴重な記録だ。侍の発想を変えられず、ハードだけ揃えてもソフトが伴わなかった、幕府軍が哀しい2014/02/01
なつきネコ@混乱中
7
歩兵隊への愛を感じてよいな。風雲児達と陽だまりの樹で、知っていたが、竹中半兵衛の子孫の下の役立たず部隊の印象が強かったが、けっこうやるのね。歴史の陰でそこそこ戦い、敗北の陰で消えてしまう。歩兵隊の創設期から崩壊まで、詳しくてわかりやすい。草創期の講武所の話とかなかなか面白い。鉄砲をやらず弓ばかりに人が集まるとか。やはり身分が高い武士が足を引っ張り、整えるのが苦労。下を集めてもうまくいかない。驚きは鳥羽伏見前に、岩倉具視が折れかけていた事、庄内藩が暴発しなければ。鳥羽伏見の敗因が指揮系統だったのは驚き。2016/06/05
伊藤チコ@革命的cinema同盟
4
小説の題材にしたらすごく難しいと思うけどすごく泣ける話になりそうな一冊。超面白かった。泣ける新書って初めて。幕末の動乱期、天狗党やら長州藩やらが暴れまくっていた時代、奇兵隊にかなり近い性質の幕府の歩兵隊。役立たずの旗本どもより町を練り歩く落ちこぼれどもを高給で雇って鍛えて参戦。当初は弱かったけど、幕府が解体してから無双が始まるwwwこういうの大好きなんだよ私www傭兵として彼らは五稜郭まで戦う。金の為親分の為、幕府への忠誠心よりかはそっちが強い。日本史の中でも珍しい軍隊を取り上げた一作です2020/04/20