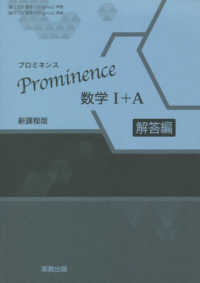内容説明
日本には現在もなお、無尽蔵と言える古文書が未発見・未調査のまま眠っている。戦後の混乱期に、漁村文書を収集・整理し、資料館設立を夢見る壮大な計画があった。全国から大量の文書が借用されたものの、しかし、事業は打ち切りとなってしまう。後始末を託された著者は、40年の歳月をかけ、調査・返却を果たすが、その過程で、自らの民衆観・歴史観に大きな変更を迫られる。戦後歴史学を牽引した泰斗による史学史の貴重な一齣。
目次
第1章 挫折した壮大な夢
第2章 朝鮮半島の近さと遠さ―対馬
第3章 海夫と湖の世界―霞ヶ浦・北浦
第4章 海の領主―二神家と二神島
第5章 奥能登と時国家の調査
第6章 奥能登と時国家から学び得たこと
第7章 阪神大震災で消えた小山家文書―紀州
第8章 陸前への旅―気仙沼・唐桑
第9章 阿部善雄氏の足跡
第10章 佐渡と若狭の海村文書
第11章 禍が転じて福に―備中真鍋島
第12章 返却の旅の終わり―出雲・徳島・中央水産研究所