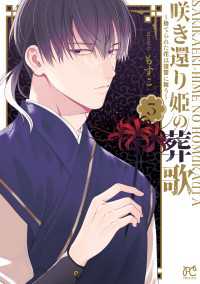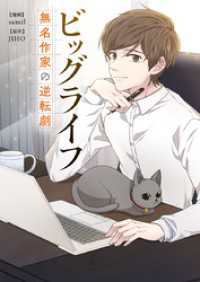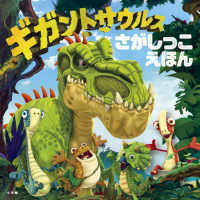内容説明
政治家はどのような方法で情報を収集・伝達するのか?通信・交通手段の技術革新が進む明治期には権力掌握の方途として、情報の価値が高まっていった。初代首相にして帝国憲法の制定者、日清戦争を勝利に導いた伊藤博文は、独自の情報システムを構築して政局運営に利用した。伊藤の幕僚団にあって敵対勢力の情報や公安情報を意のままにしつつ、メディア操縦に従事した「影の宰相」伊東巳代治は伊藤の足下を脅かす存在となる。
目次
序章 政治情報と伝達手段(情報とは何か;情報伝達手段の長短 ほか)
第1章 台頭する伊藤と政治情報(明治零年代の伊藤と政治情報―提供者から受益者へ;明治十年代の伊藤と政治情報―政治混乱の中の情報)
第2章 政治抗争と情報発受信(大隈条約改正問題と政治情報―情報低受信下の政治行動;明治二十五年新党問題―情報低発信の功罪)
第3章 権力と政治情報(伊藤博文と公安情報;内閣機密金と内閣機密費―情報発受信の裏資金)
終章 伊藤派情報システムの限界と破綻(情報システムの限界;システム破綻)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
105
政治家と情報とのかかわりを伊藤博文の生涯と絡ませて論じているもので参考になります。エッセンスは「初めに」と「終わりに」にかなりまとめて書かれています。伊藤博文と伊東巳代治の関係は非常に面白いものです。私はこれを読んでいてて最近の小泉内閣と飯島勲・竹中平蔵や安倍内閣と世耕弘成の関係を思い出しました。2015/12/29
ころこ
39
武力を公然と行使できない時代になると、相手を攻撃する方法は情報管理ということになる、というのが本書のテーマだ。暴力としての情報は権力に吸引されていくというのは、古今、不動の力学のようだ。メディアはメッセージという言葉を引くまでもなく、面談はそれだけでメッセージ性を帯び、会う会わないというだけで雌雄を決する。第3章に伊東巳代治を中心に描かれる公安情報と官房機密費は、現在の自民党を描いても殆んど変わらないようなことをしているのだろう。伊東の伊藤との距離も、伊藤の政治的立場や年齢によって付いたり離れたりする。2023/05/06
中島直人
14
権力は情報を吸い寄せる。情報の凋落は権力の凋落に先行する。他人の心はブラックボックス。危機は情報の流量を減らす。高レベルの情報が取れるのは高レベルの人物。役に立つのは面談。情報幕僚はCPU。 伊藤博文は、結局は情報を提供する部下達に踊らされる看板、責任感だけは強い操り人形にすぎなかったのではないかとの印象を受けた。権力について、情報の側面から考えさせてくれた点で刺激になった、勉強になった。2015/09/22
スプリント
7
情報戦略とは何か?という定義付けから伊藤博文の政治家としての活動を通して具体的に説明していく構成です。伊藤博文の幕僚について詳しく書かれています。いつの時代も派閥抗争はあるんですね。2017/12/23
denz
2
情報と権力を軸に、明治期の藩閥政治家たちの情報の発信、流通、阻害、誤解を書簡や日記などをたよりに彼らの抗争を描く。面白いのが、警視庁の密偵ではなく、内閣の密偵の存在。内閣を組織したものが、藩閥の政敵同士で密偵を送り、その情報を得ようと躍起になっている明治期の裏面史である。また、伊藤が中江兆民にそれなりの関心があったこと、井上毅を伊藤の幕僚や「法制官僚」ではなく、「政治家」として理解していること、伊東巳代治と伊藤との愛憎半ばする関係を描いたところなど、面白い視点がいくつかある。2011/11/30