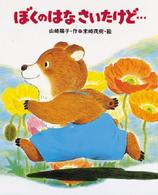出版社内容情報
・小倉百人一首・は、万葉時代から新古今時代まで五百年余に作られた和歌から精選された名歌集だが、そののち、古代から当代までを通覧してのアンソロジーは普及しなかった。そのことはわが国の詩歌の中心が短歌から連歌、俳諧へと移っていったことと無縁ではない。本書は・古事記・から現代俳句まで、旋頭歌の片歌や連歌・俳諧の発句を含めた五七五の名作を通時代的に選んで、日本人の美意識の本質と変遷を探ろうとするものである。
内容説明
『小倉百人一首』は、万葉時代から新古今時代まで五百年余に作られた和歌から精選された名歌集だが、そののち、古代から当代までを通覧してのアンソロジーは普及しなかった。そのことはわが国の詩歌の中心が短歌から連歌、俳諧へと移っていったことと無縁ではない。本書は『古事記』から現代俳句まで、旋頭歌の片歌や連歌・俳諧の発句を含めた五七五の名作を通時代的に選んで、日本人の美意識の本質と変遷を探ろうとするものである。
目次
新治筑波を過ぎて幾夜か寝つる・雑 倭建命
佐保川の水を塞き上げて植ゑし田を・夏 佐保禅尼
白露のおくにあまたの声すなり・秋 簾外少将
標の内に杵の音こそ聞こゆなれ・冬 賀茂成助
かからでもありにしものを春霞・春 良岑よしかた女
浅みどり春のしほやの薄煙・春 後鳥羽院
初時雨はるゝ日かげも暮れ果て・冬 前中納言定家
うば玉の黒髪山の秋の霜・秋 従二位家隆
春や疾き古としかけて立ちにけり・冬 前大納言為家
芦の根のうき身はさぞと知りながら・夏 後深草院少将内侍〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
文章で飯を食う
10
俳人百人のその人をあらわす一句。たとえば、小林一茶の「月花や四十九年のむだ歩き」初めて見た句だが、一茶の生涯を表していると言える。2015/10/10
てくてく
5
百人一首に対する俳句版。「新治筑波を過ぎて幾夜か寝つる」から戦後の耕衣まで、それぞれの生き方がよく表れていると編者が思った句が選ばれており、連歌から俳句に至る歴史を知る上でも、近現代の俳人の大まかな関係図を知る上でも参考になった。こちらは事典の様に、本棚に置いて何度か読むべきなのだろう。「木の葉ふりやまずいそぐないそぐなよ」(加藤楸邨)が特に印象に残った。2016/02/17
Cell 44
5
同著者の『私自身のための俳句入門』とも通ずる、和歌・連歌から俳諧が生まれてきたという考えを構成に反映させて前連歌時代から十人、連歌時代から十人、俳諧時代から四十人、俳句時代から四十人を選んで百人一句としている。日本の短詩がいかに本歌取りに支えられてきたか、付句という膨らみが価値の広がりに寄与してきたかがしみじみ理解できる。特に仁平勝との対談で、私が俳句に興味を持ったきっかけである富沢赤黄男の「草二本だけ生えてゐる 時間」の「時間」をある意味での付句とする見方には考えさせられた。2014/07/07
miyuki
3
10月26日より。和歌の好きな私としては、前連歌時代から連歌、俳諧、俳句と変化していく五七五文字詩形の歴史に、とてもわかりやすい導き方があった。古い人の句にも、その作者なりの語彙や個性、見方などがあって、それは編選者が意図したところであるけれども、立派な日本の抒情詩としての俳句の本質をみたところである。簡単な作者の経歴や俳壇での立場も書かれていて、とても勉強になる本であった。巻末の俳句詩文の本質とその文学におけるこれからの立場といった類の話も、おもしろいものがあった。2015/11/16
新橋九段
2
様々な俳人の一句を選んで並べたもので、俳句そのものの解説がされるのかと思ったけど実際には俳人の解説メインだった。参考にはなるけど期待とは違った。2018/01/16
-
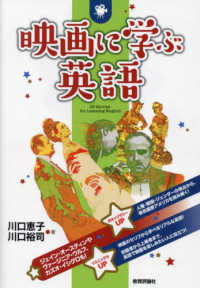
- 和書
- 映画に学ぶ英語