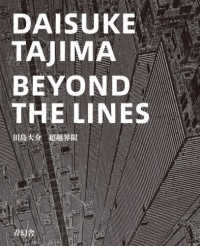内容説明
十五世紀はじめ、宦官の鄭和は永楽帝の命を承け、二万七千名の乗組員からなる大艦隊をひきいて、七回にわたり南シナ海、ジャワ海、インド洋を結ぶ航海を行い、ダウ船・ジャング船交易圏を明帝国の政治的ネットワークに転換する試みに挑んだ。明帝国の農本主義と海禁政策を採りモンゴル帝国以来の海と陸の大ネットワークから帝国を切り離し、中華秩序の再建を策したのである。鄭和の事跡を永楽帝がめざす世界秩序再編の視点で捉える。
目次
第1章 海のラクダの時代への転換と二つの「大航海時代」
第2章 モンゴル帝国の興亡とユーラシア・ネットワークの変動
第3章 大地からのうねりと中華秩序の再建
第4章 中華帝国の世界秩序をめざし陸・海に派遣された宦官たち
第5章 時代の激浪と鄭和の生い立ち
第6章 大海を渡った2万7000人の艦隊
第7章 鄭和艦隊の航跡
第8章 ジャングによる壮大な海の時代の終焉
第9章 大艦隊派遣を支えた造船業と航海技術
第10章 「大航海時代」以前のアジアの海―鄭和艦隊を支えた海洋世界
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
俊
22
明の第三代皇帝永楽帝の時代、鄭和率いる艦隊が行った大遠征について書かれた新書。鄭和は乗員約2万7千人の大艦隊の遠征を7度指揮し、その航海は東南アジアから遠くアフリカ東岸にまで及んだ。遠征の目的は各国に明への朝貢を促し、明を中心とした新たな世界秩序を作ることにあったようだ。それにしても、これだけの艦隊を組める技術、国力がありながら、海禁政策でそれを活かすことが出来なかったのは非常に残念。興隆期は無理でも、衰退期なら貿易の利益を鑑みて方針を変えても良さそうなものだけれど。それだけ国風が保守的だったのだろうか。2014/10/15
鯖
17
海禁政策をとる永楽帝の下、冊封体制を広げるため7回の大遠征に海を渡った宦官鄭和。元寇の際、4000余りの船で、1隻につき乗員28人、コロンブスは3隻の船で全部で120人の乗員。鄭和は宝船62隻に2万人が乗り込み、一隻あたり430人。具体的に数で比較すると、とんでもないなと改めて。そのような数や海図等の資料は事細かに残っているのに、これだけの大航海を成し遂げた鄭和自身について遺された資料はあまりにも少なく、墓も分からず、それが宦官であるということなのだなと思うと、ひどく切なくなった。2018/12/17
bapaksejahtera
15
気位高く蕃国からの貢を待つ大国としての中華のイメージと、大船団を率い東アフリカまで旅した鄭和の壮途との齟齬に現代の我々は違和感を持つ。本書はイスラム教徒の子弟で色目人、宦官である彼の壮絶な人生を追い、彼が中心となった明の対外活動を描く。明代に拡大した宦官制度、唐宋変革の結果招来された中華世界の国際化とこれに応ずる東南アジアとインド洋・アラビアの諸国、マラッカ海峡を境として棲み分けがなされたシナのジャンクとイスラムのダウ船等船舶の別、当時の海図や航海技術。限られた紙幅に関連事象を程よく取り纏めた好著である。2023/02/28
OKKO (o▽n)v 終活中
8
図書館 ◆何回目かの挑戦でやっと読了。これっぽっちのページ数でも一行ずつ「うー」と考えながら読むと何ヶ月もかかっちゃう(笑) ◆海巡る宦官鄭和を生んだ明朝の成り立ちからひもとき、第一次から第七次まで航海の行程を丁寧に解読、平易に解説。本来数百ページの内容か ◆同時に話題の『1421』を借りていたのだが、本書の内容から察するに「1421」のようなことは起こりえなかったのではないかと。そう考えてしまったので『1421』は読まずに返したが、もう少し勉強が進んだら『1421』を検証・比較する必要もあろうかと2017/02/02
スターライト
7
15世紀初頭、明の永楽帝らの命で7回に及ぶ大航海をなしとげた鄭和の軌跡を紹介。モンゴル帝国(元)の興亡から筆を起こし、鄭和の生涯にも触れながら当時の明の政策としての海のネットワーク作りがいかにつくられていったかを解明。また当時の航海の方法と造船技術がいかに優れていたかにもスポットが当てられ、鄭和の遠征が重層的に分析されている。宦官とされたにもかかわらず、永楽帝に仕えた鄭和の心情をうかがえる資料が遺されていないのが残念。2020/11/16
-
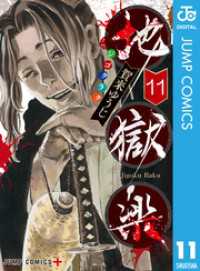
- 電子書籍
- 地獄楽 カラー版【タテヨミ】 239 …
-
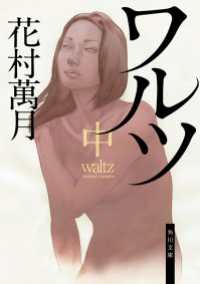
- 電子書籍
- ワルツ(中) 角川文庫