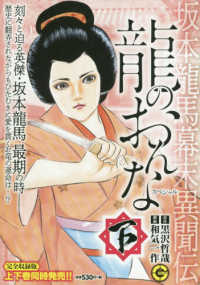内容説明
本書は、イギリス産業史を専攻する研究者が、ケンブリッジへの長期滞在を機会に、伝統的なカレッジの制度と歴史とはどういうもので、現代もそこに生きる教員や学生はどんな気質をもっているのかを、楽しみつつ苦労しながら体験した記録である。
目次
第1章 ケンブリッジ大学とカレッジ
第2章 フェローと学生
第3章 ケンブリッジでの暮らし
第4章 英会話の難しさ
第5章 研究三昧
第6章 ケンブリッジでの遊び
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
timeturner
4
作者はアメリカ留学の経験がある日本の大学教授なので、ケンブリッジのシステムを日本やアメリカの大学と比較することができ、読んでいるこちらとしては、日本、アメリカ、ケンブリッジの内部事情を同時に知ることができて面白かった。2017/01/27
Mako
2
面白かったんだけど、ケンブリッジ大学の学生生活の様子がしりたくて読み始めたので、そういう意味では大いに期待はずれ。この人は明治大学の先生らしいけれど、うまいこと余談や豆知識を盛り込みながら授業を進めていくんだろうなあ、と思わせる語り口で、読み物としては好みだった。2012/08/10
lazylazy
2
ケンブリッジの雰囲気を上手く描き出した良書。ただし、イギリス英語なら「カレッジ」ではなく「コレッジ」でしょう。cockneyも「カクニー」ではなく「コックニー」です。2010/07/06
印度 洋一郎
1
1990年代初頭にケンブリッジに留学した研究者が、その暮らしぶりについて綴っている。そもそもイギリスの大学が、近世から続く私立の「カレッジ」と呼ばれる組織と、近代になって学究機関としての機能を整備される過程で発生した国立の「学部(デパートメントやファクトリーと呼ばれる)」の複合体が更に幾つも集まったという、甚だ複雑な構造をしているので、なかなか理解が難しい。個人教授中心で大人数への講義は価値が低く見られる、博士号と教授職は必ずしも一致しない、フェローと呼ばれる教師陣だけのランチやディナー等興味深い話が多い2023/10/18
如月睦月
1
カレッジ・ライフということで学生の生活を期待して読んだが、著者は研究者としてどちらかというと教員と関わる方が多いので、あまり学生生活については書かれていない(講義を受けてもいるのでその記述は多少ある)。ケンブリッジは国立だが、カレッジは私立で別のものである等基本的なこと、教員とのランチやディナーについての話が多い。全体的に食事の話が多い印象。本人の印象とかで語られている部分も多いので、(特に英会話について)こういう風に考える人もいるんだなって思うのが良いのだと思う。2015/07/29