内容説明
日常生活での思考は推論の連続といえる。その多くは論理形式に従うより、文脈情報に応じた知識を使ったり、心の中のモデルを操作してなされる。現実世界はまた、不確定要素に満ちているので、可能性の高さを直観的に判断して行動を決めている。推論はさらに、その人の信念や感情、他者にも影響される。推論の認知心理学は、これら人間の知的能力の長所と短所とをみつめ直すことによって、それを改善するためのヒントを与えてくれる。
目次
1 人間は論理的に推論するか(形式論理と日常的推論;論理的推論の認知モデル;帰納的推論―一を聞いて、十を知って、三誤る)
2 確率的な世界の推論(確率・統計的な現象に対する理解と誤解;ベイズの定理をめぐる難問・奇問;確率・統計問題での推論のしくみと学習)
3 推論を方向づける知識、感情、他者(推論は知識に誘導される;因果関係を推論する;自己の感情と他者の圧力)
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





Hr本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かるかん
61
推論とは、使われる場所によって行われ方が違う。また、その人の支持する考えや心理状況にも左右される。こういった本を読むことで、無意識化で誘導的に導き出されてしまう自身の推論に対して疑問を持つようになるだろう。その推論には自分の願望やバイアスが含まれていないのかを少し考えるだけでも世界の見方はもっと広がっていく。 同様に、自分に対する批判もそれを真摯に受け止めたり中立的な立場で考えることでより一段上の人間に成長できるに違いない。2016/01/17
hit4papa
27
本書のメインテーマは、人間の推論について心理学的な立場から眺めてみることです。認知心理学や社会心理学の推論研究に基づいているので、確率論や統計学が苦手でも理解できるでしょう。読み返す度に違った気づきを与えてくれます。折々、再読したい一冊です。2013/04/01
デビっちん
25
思考とは推論の連続です。その推論を細分化して、論理的推論、確率的推論、日常場面に於ける推論に分け。3つの切り口から考えることを解説されていました。人間の行う推論活動には、バイアスやエラーが多く含まれていることが様々な実験のデータからわかりました。それを自覚した上で、論理学や確率、心理学という道具を使うことで、より洗練した思考をすることができますね。色々な角度から補正できる中、この3つを選択したことにバランスの良さを感じました。2017/06/03
スパイク
25
ほとんどの人は「だいたいにおいて」うまくやっていくための思考法をとる。だた「だいたいにおいて」でしかないということを忘れてはいけない。この本が(興味深く読んだが)面白くなかったからといって市川センセの他の御本すべてが面白くないということではないし、私がこの本を理解するに必要な知識を蓄えた後に再読すれば、どわっはっは~と笑い転げるほど面白く感じるかもしれない。(岩波赤本とまではいかないけれど)中公新書だからちょっと知的な感じがして面白くもないのに興味深いなんて書いてしまうバイアスかかっているかもしれないね。2015/07/04
おおにし
19
ベイズの定理の事後確率の問題は、理屈では確かにそうかもしれないがどこか騙されているような気がしていた。しかし、本書で紹介されている図式による説明を聞いて、なるほどと納得できた。それでもベイズの定理は私には難しいな。2025/05/06
-
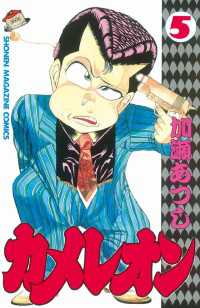
- 電子書籍
- カメレオン(5)





