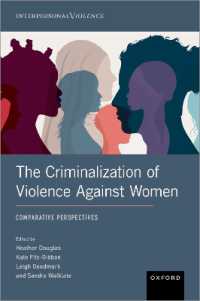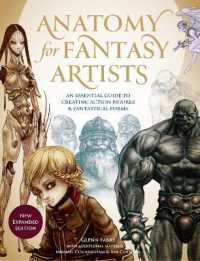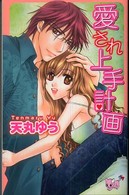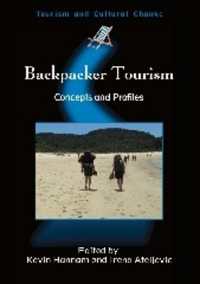内容説明
日米開戦をめぐって海軍は、陸軍との対立の中で苦渋の選択を迫られ、最終的には終戦工作をリードして日本を破壊の極みから救った―という史観は正当といえるのか。自立した政治組織・権力である海軍は時局をいかに認識し、日米開戦をどう捉えていたのか。また海軍穏健派による東条内閣打倒工作と終戦工作の最終的狙いは何であったのか。「戦争責任」の視点から「高木惣吉史料」等、新史料を駆使して、昭和初期政治史を再検討する。
目次
序章 日本海軍の時局認識
第1章 欧州情勢の変化と海軍
第2章 日米開戦の前提
第3章 日米交渉の展開
第4章 東条内閣打倒工作
第5章 終戦工作の真相
終章 海軍の戦争責任
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
107
いつも開戦や終戦の資料やノンフィクションを読むたびに思うのですが、海軍がひとりいい子であるような書き方をしているものが多いと思われます。戦争の場合は海軍や陸軍関係なく戦略にのっとって、戦術を実行していくべきなのでしょう。どこの国にでも派閥などはあるのですが、日本の場合はそれがひどすぎるような感じで、陸軍内部でもいくつかの派閥はあります。海軍はその点動きがうまく先を読む力情報聴取能力が高かったのだと思います。それがよくわかりました。2015/12/31
NoControl
9
タイトルに終戦工作とあるが、開戦に至るまでの海軍のスタンス、動向も結構な紙面を割いて記述している。今でも尚唱えられる海軍善玉説が実際にはどうだったかを検証しており、一元的に善玉悪玉で区別して議論するには難しい程度に海軍も開戦、決戦に一定の推進力があったことが伺える。また終戦工作はあくまでも天皇制という国体護持を主目的としており、国民の生命・財産は考慮されていないことと、重臣や各指導部も決定的な指導力は持たず、「聖断」以外にも天皇の継戦への意向を忖度する形で各種大綱が決定されてたことは今一度認識すべき。2020/10/11
Toska
8
海軍絡みでは開戦時の記述が手厚く、終戦工作については宮中グループの存在感の方が大きくなるので、ちょっと看板倒れな印象。とは言え読み応えは充分。まとまりがなく無定見で無責任、そのくせ組織の利益はきちんと追求する海軍の「ズルさ」が目につく。もっとも、同様の特徴は陸軍や政府、重臣、さらには天皇にも共通しており、こうした諸勢力の寄り合い所帯では戦略の立てようもなかっただろう。結局、明治憲法体制がダメだったということになってしまうのか。2022/07/16
樋口佳之
8
戦後日本社会は、いわば「日本陸軍的」なるものを捨てて、「日本海軍的」なるものを選ぶことで戦前的な本質を保守しつつ、戦後的な形式を取り入れたといえよう/最近はそこさえ危うくなっている。宮廷グループが引きずられていない様子なのが救いかもしれない。2016/07/28
moonanddai
5
戦前の重要な政治セクターである海軍の政治姿勢についての書。対英米戦争を不可避のものと認識しながら、結局は陸軍との「間合い」と自らの存在感を基準に立場を決定して行き、「親英米」、「親独」も理念ではなく、方法だったということでしょうか…。最終的には「陸軍悪玉論」に持ち込んだ海軍や宮中グループの動きはしたたかそのもの。そして「日本の一番長い日」へと続く…。2013/01/03