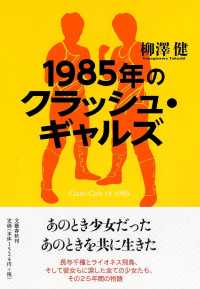内容説明
1775年に英国を模して創設されたアメリカ合衆国海兵隊は、独立戦争以来、2度の世界大戦、朝鮮・ベトナム・湾岸戦争などで重要な任務を遂行し、遂にはアメリカの国家意志を示威するエリート集団へと成長した。はじめは海軍内でとるに足りなかったならず者たちが自らの存立を懸けて新たな戦術を考案し、組織の自己革新をなしとげたのである。本書は、その戦績をたどりながら、「最強組織」とは何なのかを分析する試みである。
目次
第1章 存在の危機
第2章 新たな使命の創造―水陸両用作戦
第3章 教義の実践―南太平洋方面作戦
第4章 教義の革新―中部太平洋方面作戦
第5章 革新への挑戦―水陸両用作戦を超えて
第6章 組織論的考察―自己革新組織
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
107
最近参謀組織などに関する本を読んだりしていますが、この本もアメリカの軍隊における組織的な分析を専門の野中先生が分析しています。アメリカ海兵隊の歴史はそのままアメリカの歴史であるといわれています。結構存立の危機などがあったようですが、それをばねにしてきちんとした存立理由を作り出すところが日本の官僚組織と違ってすごいと思いました。2016/01/16
skunk_c
61
『失敗の本質』の共著者で、組織論が専門の先生が、かなりマニアックに書いたもの。湾岸戦争後の1995年末の刊で、オスプレイが世に現れた頃。ブートキャンプを実地に見聞(最近はCATVでも見ることができるが)するなどかなり踏み込んだ内容。敵前強襲と橋頭堡確保に関しては、第2次世界大戦時にその方向性が確立したようだ。全体にちょっと「褒めすぎ」な印象で、特に最後の組織論については、理想化しすぎてる気がした。また、ベトナム戦争自体の評価はほぼ首肯できるが、アメリカと海兵隊の立ち位置については、別の視点も必要と思った。2022/02/06
さきん
26
もはやアフガニスタンな内陸にもヘリボーンで乗り込む海兵隊。始まりは、ワシントン将軍もいやいやで居酒屋での強引な勧誘から始まった。米西戦争で海軍が活躍したのと同時に注目され始め、第一次世界大戦で精強さを披露、太平洋戦争で日本軍に鍛えられながら世界で一番強い組織として成長していった。常に存在理由を問われる存在であるからこそ、敵前強襲上陸から即応部隊として新たな境地を開いている。2021/10/04
James Hayashi
26
1775年設立、機動力を駆使し侵攻作戦を速やかに実施するForce in Readiness (即応部隊)かつ銃剣から核搭載機能をもつ航空機までユニークな強襲遠征部隊。ペリーが来日した時も200人の海兵隊を引き連れ、太平洋戦争のガダルカナル、タラワ上陸作戦、朝鮮戦争、べ戦争などの活躍を表記。NavyとAmyの中間の水陸両用作戦を駆使し存在感を見せつける。気になるのは垂直離着陸機のオスプレイ(海兵隊と深い関係)。場所を選ばず、ヘリコプターより速く航続距離も断然長い。安全性を問題視されているが実際どうなのか2017/09/07
無重力蜜柑
10
海軍でも陸軍でも空軍でもないアメリカの第四軍、海兵隊。独自の固定的なドメインを持たないがゆえにアイデンティティに悩み、技術の発達や情勢の変化に合わせて自己革新を遂げてきた組織の変遷を経営学的に辿る。なんとなくアメリカのエリート部隊くらいのイメージしかなかったので面白かった。とはいえ20年前の本なので情報のアップデートが必須(特に世界規模の即応部隊という構想は米空軍が冷戦後に追求した筈だし)なのと、著者がかなりアメリカと海兵隊に思い入れがあるようなのでさっぴいて読まねばならない。2022/04/30
-
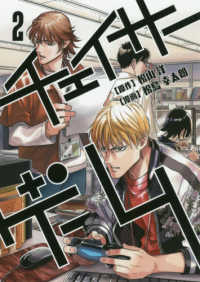
- 和書
- チェイサーゲーム 〈2〉