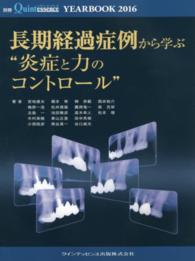内容説明
自由民権期の輝かしい理論家の1人で、板垣退助のブレーンとして活躍した植木枝盛は、今後歿100年にあたるが、その短い波瀾の生涯を、同郷の中江兆民、馬場辰猪、小野梓とのかかわりをも交えて描く。とくに本書は、維新の混乱の中で失われたアイデンティティを求めた枝盛の苦闘と、伝統思想に依拠しつつ西洋の新しい民主主義思想を受け容れ、ラジカルな思想形成を行なった枝盛の心的過程と自我表現とに新たな光を照射する。
目次
第1章 青少年時代
第2章 立志社の活動家として
第3章 民権運動の広がりのなかで
第4章 自由党での活動
第5章 帰郷
終章 少壮政治家として
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ジュンジュン
8
入門書としては×、求めていたのとは違った。板垣退助の片腕にして、自由民権運動のイデオローグとしての関わり(と生涯)が知りたかったが、著者のアプローチは政治思想の変遷と解明に向けられている。外国語が読めず、翻訳書での独学のため、ルソーの社会契約論を十分理解していなかったとの指摘は、自由民権運動の特徴をも示しているように感じた。2022/03/10
Takao
2
1992年8月25日発行(初版)。安政4年(1857年)に生まれ、1892年1月23日、35歳で死去した自由民権の思想家・植木枝盛。本人の書き残した「日記」や読書目録などを軸に彼の「思想」を中心に論じられている。彼の思想形成に関する記述などはとても難解に感じたが、大まかな行動については初めて知ったことも多かった。枝盛は全国各地を遊説しており、1884年7月には長野(7/12)から小諸(7/13)を通過している。故郷の東御市に何か枝盛の足跡が残っていないか興味を持った。2019/10/02
しんすけ
1
植木枝盛の基本は自由である。本書も、「心の自由がなければ人間本然の性分を全うできず、したがってほとんど人間と云い難い」と要約している。しかし、国や体制にとり「自由」とは忌み嫌う対象でしかない。公僕に過ぎない卑しき官僚が暴政に手を貸すのはその証しである。枝盛は暴政に対しては革命をもって対抗するを人民の権利と考えていたようだ。これは憲法概念の創始であるロックの『市民政府論』に通じるものがある。35歳で病没(明治政府による毒殺との説あり)したため、それは体系に到るものとはならならなかった。惜しむべきことである。2015/10/08
SK
0
63*憲法に関連して気になっている人物なのだが、そういった記述が少なくて残念。心を拠り所にする。自身を天皇に擬していたとは、驚いた。枝盛の登楼に触れていたり、辛口の突っ込みが入っていたり、著者の植木枝盛に関する愛情を、あまり感じなかった。2016/03/12