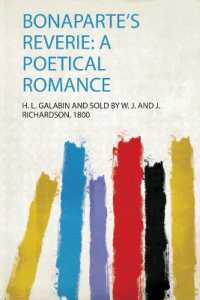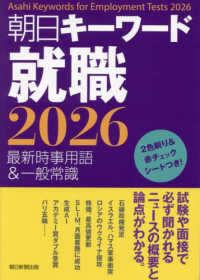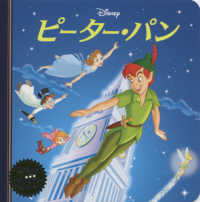内容説明
強大なカリスマ性をもって、絶対主義政策・中央集権化を支持する官僚・公家・寺社勢力を操り、武家の身で天皇制度の改廃に着手した室町将軍足利義満は、祭祀権・叙任権などの諸権力を我が物にして対外的に〈国土〉の地位を得たが、その死によって天皇権力簒奪計画は挫折する。天皇制度の分岐点ともいうべき応永の時代に君臨した義満と、これに対抗した有力守護グループのせめぎあいの中に、天皇家存続の謎を解く鍵を模索する。
目次
天皇家権威の変化(親政・院政・治天の君;改元・皇位継承・祭祀)
足利義満の王権簒奪計画(最後の治天―後円融の焦慮;叙任権闘争;祭祀権闘争;改元・皇位への干与)
国王誕生(日本国王への道;上皇の礼遇;百王説の流布;准母と親王元服)
義満の急死とその後(義満の死と簒奪の挫折;皇権の部分的復活;戦国時代の天皇)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
305
本当かどうか不明だが足利義満が当時最大限の権力を持ち、朝廷に入り込んでたのは事実だと思うし、そういう考えもあったんだろうなと思った。もし義持が父の遺志を引き継いで引き続き朝廷にあたればまた歴史が変わってただろうな。ここで皇室が存続したことで歴史的存在になり、権威が飛躍的にあがったことを考えれば当時の後円融上皇の苦労は無事に報われたんだなと考える。歴史にイフはないが本書は中々面白い思考実験だな。2016/06/18
まえぞう
28
源氏と日本国王を読むと、なぜかこちらも再読したくなります。両著とも少し議論が強引だと感じますが、結論に至る種々の情報はなるほどなと思わせてもらえます。さて、今度はいつ再読することになりますかね。2025/11/14
Toska
21
久々に。本書で主張されている「足利義満の皇位簒奪計画説」は、その後の研究の進展でほぼ否定し尽くされた感がある。ただ、義満の強烈なキャラクターや、室町幕府と朝廷との複雑な関係に注目を集めたことは、本書の重要な功績であったように思う。著者独特の活力ある文体と相まって、いま読み返しても実に面白い。ここから室町時代への関心が広まり、新たな研究の呼び水になったと考えれば、所説の当否はどうあれ価値ある一冊。勿論、今谷さん自身がそれで納得しているかどうかは分からないが。2025/05/29
まえぞう
20
源氏と日本国王を読んだので、こちらも再読しました。有名な本ですが、やっぱりしっくりしません。歴史学者の方法は帰納的なものだと思っているのですが、まず結論があってその論証に都合のよい文献を選んでいるように見えてしまいます。2023/07/17
まえぞう
15
話題の「応仁の乱」の前に、同じ中公新書で1990年代に話題になった本書を再読しました。ちょうど応仁の乱の直前の時代ですが、参考になりました。ただし、義満が王権の簒奪を考えていたという結論は、少し急ぎすぎのように思いました。2017/03/05