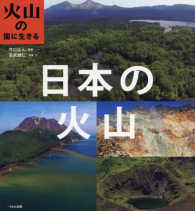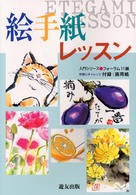内容説明
多民族、多言語、多宗教の国インドでは、今日ヒンドゥー教徒が総人口の8割をしめ、かれらは文化、政治、経済に圧倒的な力を及ぼす。ヒンドゥー教は信仰と生活実践を一体化した宗教で、特有の社会制度、法律、倫理道徳の体系をもつが、その原型は記元前後の編纂と推定される『マヌ法典』で仕上げられた。本書では、今日もインドの社会体制、人びとの価値観と生活の深層部を支配する『マヌ法典』を、正確に、わかりやすく紹介する。
目次
第1章 『マヌ法典』の世界観―世界創造とヴァルナ体制
第2章 『マヌ法典』の人生観
第3章 行動の準則
第4章 罪と贖罪
第5章 犯罪と刑罰
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
dosurasan
1
ブラフマンの口からバラモン、胸からクシャトリヤ、腕からバイシャ、足からシュードラ2014/08/01
in medio tutissimus ibis.
0
マヌ法典は0±2世紀、マハーバーラタと同時期に、ウパニシャッドの思想と苦行主義の隆盛と既存社会の崩壊を受けて編纂されたダルマシャーストラ文献の白眉である。法典と訳されるもののその実態は上位バラモンと王の理想的な在り方を、ヴェーダとヴァルナ制に基づき、現実との妥協を視野に入れて説くものであり、宇宙論をも包有する。仏教の関わりなど弱点はあるが、ヒンズー教に抱いていた疑問が多く解消された。名誉ひとつで飯食ってる人種の人生は想像を絶する。「おいは恥ずかしか!生きておられんごっ!」とかがギャグで済まねぇんだな……。2017/12/07
まっちゃん
0
ためになりました。2016/01/24
うちこ
0
「法典」なので、リグ・ヴェーダにある内容をより人間社会用にシステマティックに定義したような内容。「司法の神ヴァルナは人間のいかなる行為をも見逃さない。この考えは最も古い時代から人々の心の中にあった。(194ページ)」とあるのだけど、罪と罰の感覚は啓示宗教のそれ(アッラーは全部見ておるよ、秤にかけるよ、というような)ではなく、「それぞれにお似合いの地獄を用意しているよ」という内容。人が人を裁くことを神が命令している啓示形式ではなく、神がこう決めたということにしてバラモン階層で塗り重ねている。2014/06/07