内容説明
角筆は木製・竹製等の筆記具であり、尖端で和紙の面を凹ませ文字や絵をかいた。毛筆がおもで紙が貴重であった時代に、角筆は今日の鉛筆のように使われ、その迹は凹線として残る。王朝時代から「かくひち」として物語に登場するが、具体相は不明であった。本書は角筆文献の発見者である著者が文献の秘める世界に、埋もれた北九州の文化、王朝人の日常口語や俗語の謎を解き、法隆寺壁画の技法や木簡から中国古代に角筆の源流を見る。
目次
角筆と角筆文献(王朝物語の世界;角筆文字との出逢い;出現した“幻”の角筆用具;埋もれた北九州の文化;角筆文献の内容と言葉の性格)
角筆の言葉(女手のもう一つの世界;王朝人の日常口語をかいまみる;俗語を掘り起す)
中国大陸へ―角筆の源を求めて(法隆寺金堂壁画から中国唐墓の壁画へ―絵画史の一問題;中国大陸2千年前の古代へ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Miyaz
0
星5つ。角筆について筆者が一般向けに書いた初めての本。角筆というほとんど知られていない筆記用具に注目して、その記述がある書や木簡を発見し解析している。角筆で書かれたものは、「かしこまった」「あらたまった」ものでなく日常の「言葉」が書かれている。筆者は書かれた当時の言葉がわかるという。かな文字がどのようにできたかも言及されている。私には新たに知ることばかりでとても興味深い本であった。「おれ」という言葉が平安時代?から、相手に使う言葉であり、また自分を指す言葉でもあるというのもその一つである。続巻を期待する。2018/07/27
-
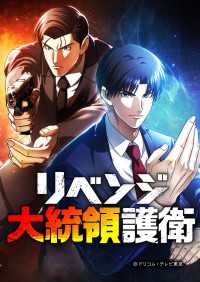
- 電子書籍
- リベンジ大統領護衛 第45話【タテスク…




