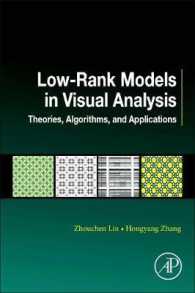内容説明
後藤新平が、台湾総督府民政長官や満鉄総裁として植民地経営に辣腕を振い、鉄道院総裁として国鉄の発展の基礎を築き、都市計画に雄大なヴィジョンを示したことは今日なお評価されるが、外交指導者としては、ほとんど忘れられている。しかし、当時にあっては矛盾と飛躍に満ちた言動ながら後藤の人気は高く、「唯一の国民外交家」とまで評されるほどであった。本書は、外交指導者の条件を問いつつ、後藤新平の足跡を辿る評伝である。
目次
序章 医学と衛生(青年時代;衛生局時代)
第1章 台湾民政長官(台湾統治の基礎;台湾の「文明化」;清国とアメリカ)
第2章 満鉄総裁(総裁就任;初期経営方針―大連中心主義と文装的武備;満鉄をめぐる国際関係)
第3章 官僚政治と政党政治(第二次桂内閣時代;在野時代;大正政変と桂新党)
第4章 第一次世界大戦と日本(大隈内閣批判;寺内内閣の成立;中国とロシア)
第5章 失われた可能性(世界大戦後の世界と日本;ヨッフェ招請と帝都復興;晩年)
後藤新平年譜
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
145
中々面白い経歴を持ってる方だなと驚く。台湾統治、東京の復興、満鉄と日本の要所をビジョンを持って動いてる感じ。 今の日本の政界には中々いない人材だと思う。2025/07/13
skunk_c
63
35年前、著者40歳の頃の著。後藤新平の外交とヴィジョンに焦点を当てたとのことだが、評伝として十分読める。医学を学ぶ中、衛生からインフラ重視の姿勢(日清戦争終末期の検疫)から台湾での都市計画と進むあたりから、のちの満鉄経営や日本の鉄道の広軌化、さらには関東大震災後の東京復興都市計画に続く一貫した姿勢、一方で国家・社会を生命体的に捉えることにより、上からの高圧的な支配ではなく、その社会の伝統や習慣を認めていく姿勢があったとの指摘は面白い。こうした姿勢が中国やロシア(ソ連)との外交にも貫かれているとの見方だ。2023/04/04
Tomoichi
20
業績に対してどれだけ現代人に認知されているかわからないが、彼が近代日本において果たした役割は多い。今なら疫学についてか又は関東大震災後の復興計画だろうか。しかし彼が拘った「調査」、これこそが彼が残した最大の遺産ではないだろうか。叩き上げ明治人の物語です。2020/08/08
KF
18
後藤新平については臺灣に関わる三大偉人(他の二人は児玉源太郎と八田與一)と思っており、臺灣から満洲に移っていこうは難しい印象だけ思っていた。本書で臺灣時代を含むその生涯を読んだ気分。巻末の年譜や参考文献まで興味深く感じた。後代の我々の目で見ると「優れた個性」なのかもしれないが、同時代人には「理解し難い個性」だったのだろうと思う。その個性を操る事が出来たのが児玉源太郎だったのではないだろうか。筆者は総裁にも外相にも不向きであったと記している。全体の上に立ってチームワークの長になるには難解過ぎたのだろう。2025/06/29
健
16
読み応えあった。医学を修めたという事もあって、国家を生命体として捉え、健康体を造るという考え方が新鮮だった。日本政府が手こずって手放そうとしていた台湾に赴任し、現地の風俗、歴史、地理に基づいて統治することで民心が刷新されて大いに発展し、親日国となったというのが大変示唆的。後藤新平が担当していなかったら、今の朝鮮半島のような反日国となっていた可能性大で大変な功績だと感じだ。その後、満鉄総裁になるが、朝鮮総督の話もあったようで、そうなっていたら東アジアの情勢は変わっていたんじゃないかと思ってしまった。2025/12/27
-
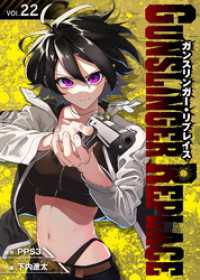
- 電子書籍
- ガンスリンガー・リプレイス(22) C…
-
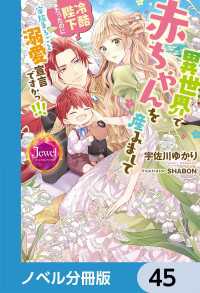
- 電子書籍
- 異世界で赤ちゃんを産みまして 冷酷陛下…