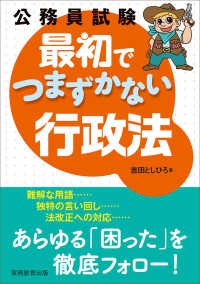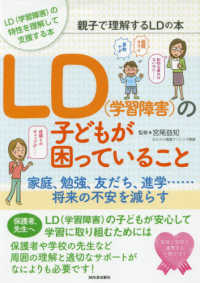内容説明
遊女とはかつて「性」を「聖なるもの」として生き、神々と共に遊んだ女たちであった。本書は従来の遊女史の枠を越え、万葉集、謡曲、梁塵秘抄、から御伽草子、近松、西鶴、荷風、吉行淳之介に至るまで、文学に現われた遊女像の系譜を辿りつつ、文化を育んだ「遊び」の姿を明らかにする。ホイジンガの遊戯論に示唆され、比較文学の手法を駆使して試みられた遊女論であると共に、新しい文化論、女性論への展望を拓く意欲作。
目次
第1部 色恋と歌舞の女神(イシュタルの章―古代における性と遊びの位相;ミューズの章―歌舞の菩薩;和泉式部の章―色好みと歌の徳;高尾太夫の章―愛欲の女神;花子の章―「花」の体現)
第2部 薄幸の乙女たち(松浦佐用姫の章―聖なる花嫁;妙の章―無常の悟り;小野小町の章―流浪の聖女;お初の章―愛の殉教者;お雪の章―慈愛の聖母)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
49
生と死は相反しているようで、その実は隣り合わせの位置にある。「性」と「聖」のふたつの「せい」が、本書において近接して語られるのはその為だ。「せい」によって越境することが出来るのは女性であり、その存在を「遊女」と呼んでいる。第3章では実際には遊女でなかった小野小町的なものを①色好み②和歌の才③美貌をもって「遊女」と呼んだ。問題は、この「遊女」は男性から見て女性を規定したものであり、男性性を内面化したものだということにある。フェミニズムも一側面だけだと思うので、双方成り立たせることは出来ないないものだろうか。2023/04/28
まこ
9
時代とともに遊びが性的なものではなくなり、宗教でそれらは否定される。遊女が放浪する存在だったり隔離したりしてどうにか遊女の持つ神秘性を保とうとした。そのために遊女は卑しい存在にされてしまうがそこをうまく物語では「悲劇のヒロイン」に昇華していく。本書では街を出ようとした女たちは結局また戻ってくる、それはなぜかについて問いている。「闇の女たち」に出てきた女性たちはお金やそれ以外の生き方しか知らないと言っていた、というか、慣れた仕事。2020/11/21
die_Stimme
5
古代から文学作品にあらわれてきた「遊女」像を分析することでその意味合いの変容を見ていく。とても面白かった。一つ気になるのは、何度か登場していずれもネガティブな意味で言及される「フェミニズム」への態度。遊女は「聖性」を持っていたというところから語り起こしていく以上、たしかに現在も自ら望まずに性業界で働く人のおかれた状況を肯定してしまうように受け取られることもあっただろう(事実と当為の錯誤、とまで言えるかは分からないけど)。でもそれでフェミニズムを批判するのは、主語を取り違える、別の錯誤に陥っているのでは。2025/01/19
米村こなん
4
【公共図書館】遊女と無縁(所)との関連性を知りたかったが、本書は日本文学史における「遊女」の変遷を辿るのに終始し、知りたい情報が得られなかった。だが、「遊女」の聖性を文学的に明らかにする文献として読める。また、安易なフェミニズムを棄却する文芸批評とも言えようか。2016/03/28
小谷野敦
3
著者本人も今では認めていないだろう。売れているため絶版にならないらしいので教育的配慮から復活させる。一点にしないのは一点をつけたくないからで、ユングの原型を流用したこの本については「聖なる性の再検討」という論文で詳細に批判したしウェブ上にもある。なお近世娼婦神聖説は松田修が言いだしたものだ。1987/11/01
-
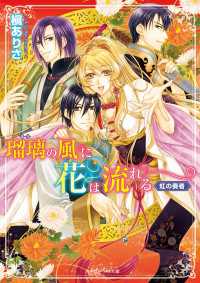
- 電子書籍
- 瑠璃の風に花は流れる 虹の奏者 角川ビ…