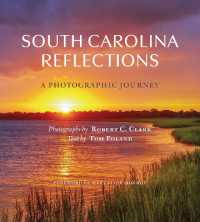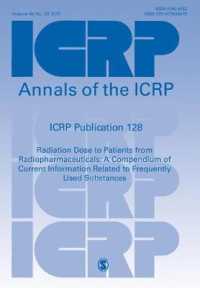感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
107
私は西洋経済史関連では大塚久雄先生の本の読みますが角田先生の本もかなり好きです。お互い考え方には結構溝があるようでかなり論争をしておられますが。特に角田先生は西洋の文明や文化の発展などに貢献したモノについての歴史的な分析をされています。この本も時計というものがどのように発明されて人々の生活に活用されてきたのかを和時計も含む様々な時計の歴史を探っています。2016/01/03
kaizen@名古屋de朝活読書会
82
時計は船舶、鉄道などの交通において重要な役割を果たす。時間と空間が切っても切り離せないものであるかのように。交通と時計について、具体的に知らなかったことが沢山あり、とても参考になった。 ps. 野口 悠紀雄著 「続「超」整理法・時間編―タイム・マネジメントの新技法 」 の参考文献に本書を掲載。2014/06/08
テイネハイランド
16
図書館本(1984年刊)。近世から現代において、「時計がどのように英国や日本などで普及し、その当時の人々が時間についてどのような意識を持っていたか」について主に紹介しており、初めて知った項目や新たに興味をもった項目が多くあり読んでよかったと思います。中でも「ガリヴァーの懐中時計」の章と「英国で標準時がどのような事情で普及したか」について語った箇所は面白い。ひげぜんまい/デーテント脱進機/二挺テンプ式和時計など、時計に使われている技術面についてもっとくわしく掘り下げた啓蒙書があれば読んでみたくなりました。2016/10/01
kenitirokikuti
6
2014年の復刊もあるが、本書は1984年のもの▲「奥の細道」の時計/「細道」に細かな旅の記録は欠けているが、芭蕉の従者が日記を残している(『曽良旅日記』)。当時、ケンペルが懐中時計を持ち込んでいたが、芭蕉が機械式の懐中時計を持っていた形跡はなく、紙製の日時計も同様。すると、芭蕉が旅した山奥まで寺院の梵鐘が時鐘となっていたとしか考えられない。当時の村の数と、梵鐘の数の推定は五万ほど。元禄のころ日本の銅生産がピークにあり、そこで多数鋳造されたらしい。2017/10/08
印度 洋一郎
5
人間が時間を知るための道具である時計。日時計や水時計は兎も角、中世ヨーロッパが生み出した機械仕掛け時計は、人間の時間に関する概念を変えた。時間を守る、時間通りに行動するという身体感覚は近代化、工業化に欠かせないものだった。しかし、それは人為的な概念であり、皆が馴染むまでに数世紀を費やす。特に工業化が進んだイギリスでは労働者への啓蒙が一大事。対して不定時法の日本では、ヨーロッパから入ってきた定時法の機械仕掛け時計を和時計にアレンジするための工夫が、後の近代化に役立った。時間とのつきあい方を考えさせる本だった2014/06/28