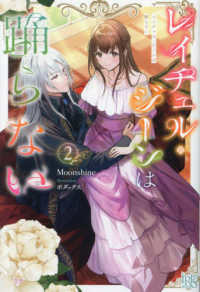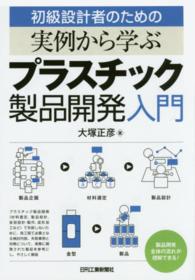感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
わんつーろっく
16
戦災と進駐軍の接収により、荒廃していた横浜の復興。60 〜70年代に横浜市長として六大事業を手掛けた飛鳥田一雄氏のブレーンとして、企画調整局でまちづくりを推進した著者の手法を学ぶ。中央官庁から「横浜市はいつから独立国家になったのかね」と言われれは「国は一向にその対応をしないではないか」と。目先の損得ではなく、長い目で見据えた横浜のまちづくりは、今、その軌跡を辿れば、あぁあの時のご苦労で、高速道路が地下化し、緑豊かなプロムナード、つい最近日本一になったベイスターズのスタジアムも、そうだったのね・・と。2024/11/03
jackbdc
11
都市デザイン横浜展に足を運んで驚いたのは、港ヨコハマのまちづくりに関わった人たちが先人や自分たちの仕事振りに誇りを持っており、それを隠さないこと。同行した知人から進められて本書を手に取った。出発点となった約50年前からの意欲や苦労話が包括的に述べられている。このエッセンスが展覧会に表出していたのだと気付く。まちづくり界隈において1.時代を超えたマインドの継承、2.開放性の確保、この2つは理想であり国内で成功事例は少ないと思う。港ヨコハマの成功は特殊性があったとしても他地域が学ぶべき要素もきっとあるだろう。2022/04/10
miffy.x.
2
☆×100 良書でした、先見の明があるとはこういう方のことを言うのですね2021/12/04
KN69
2
すごい本だった。横浜のまちづくりについては、幾度となく聞いてきたし、それなりに詳しいつもりでいたけれど、現場”企画調整室”にいた田村氏から語られる30年スパンのまちづくりの熱量は圧巻だった。プロジェクト方式によりわかりやすい形で船頭をとりながら、ここのプロジェクトは連携し、接続し、ひとつのオーケストラの楽曲のように編み上げられていく。また、地味な作業の積み重ねがヨコハマのまちづくりの本質ではないかと感じた。たとえば、山下公園のトイメンのペア広場。壁面後退によるゆとりある並木道の創出。2018/02/03
yoyoyon29
1
・1968.4.5横浜市企画調整室:都市づくりを総合的にすすめる ・横浜歴史:①江戸:新田開発幕末101戸の半農半漁⇔東海道宿場町、②1853ペリー来航、1859横浜開港で中央部に役所+東に外国人居留地+西に日本人町 ・1955-(S30-)横浜:戦災により壊滅、接収により関内牧場化(黒澤明「天国と地獄」)、東京のベッドタウンとして無秩序な開発 ・1960-:市民参加や自治体の自主性の気運→1963-飛鳥田政権で本格化 2020/09/14
-

- 和書
- 縁起する浄土