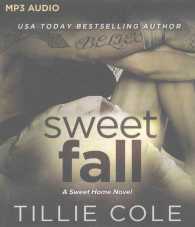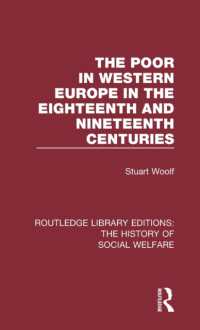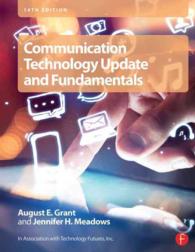感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
塩崎ツトム
23
日本の被差別部落やそこに暮らす被差別民について知らない人はいないと思うが、ヨーロッパでも同じく皮革業者や刑吏が被差別階級として、それも日本の被差別階級とまさに鏡写しのようになっている。本書では中世ドイツの処刑が秩序を回復させる神聖な行いから、都市や王権の発達とともに「穢れ」として扱われていったかを、西洋の先行研究を元に解説。外科医術や娼館を営む権利も、ひどい差別の対価として刑吏には与えられていた!2025/05/29
棕櫚木庵
18
記憶に残る要旨3点.1) ヨーロッパ古代・中世初期において,犯罪は社会(コスモス)の秩序を乱すことであり,処刑は,その乱れを正常に戻す呪術的祭祀だった.儀式が終わった時,犯罪者がたまたま死に至っていなくても,殺し直したりはしなかった.2) やがて,処刑は犯罪者個人への報復あるいは社会への威嚇となり,刑吏(職業的死刑執行人)が登場する.彼らは,恐れられると同時に忌み嫌われ,賤民として差別された.3) 刑吏を差別から解放したのは,19世紀の近代的国民軍の創設だった.軍役の下の平等.→2024/10/03
安南
14
17世紀、神聖ローマ帝国を舞台にした小説『聖餐城』を楽しむために。主人公の恋する少女が刑吏の娘という設定なので。かつて神聖な儀式であった処刑が、12〜13世紀頃から「名誉をもたない」賎民の仕事に変わっていく、職業としての刑吏が出現し、彼らは蔑視され激しい差別を受けるようになる。その蔑視、差別の根元は何かを探る、スリリングな研究書。いつも思うけれど、阿部氏の文章は読みやすく飽きさせない。資料のつもりで斜め読みするつもりが、しっかり読み込んでしまいました。2013/04/22
サアベドラ
13
中世ドイツの刑罰と刑吏を取り巻く社会史。『ハーメルンの笛吹き男』で有名な阿部謹也の初期の著作。1978年刊。中世初期の刑罰には古ゲルマン的儀式性・宗教性が見られたが、時代が進むにつれてそれらが失われ、同時に刑吏に対する人々の眼差しは尊敬から軽蔑へ変化し、後期には棺も担いでもらえない立派な賤職にまで堕ちてしまったというお話。基本的にドイツの先行研究の受け売りで、今から見るとそこまで断定して大丈夫なの?と言いたくなるような記述も見られるけど、社会史が珍しかった当時の日本では斬新で新鮮と受け取られたのかな。2013/12/16
日の光と暁の藍
8
中世の刑吏には、一つの物語があることを知る。中世において、「特定の職業の担い手が差別の対象とされ」(P15)ていた。日本でいえば、非人と呼ばれた人々。ヨーロッパの場合は刑吏がそうであった。刑吏の子は刑吏以外の職業に就けなかった。また、刑吏の子の出産や刑吏の埋葬を手伝う者は賤民に落ち、同職組合(ツンフト)から除名されたという。阿部氏は本書で、かつて神聖な儀式であった処刑が、なぜ卑賤な行為へと変化したのか、を先行研究を批判しつつ、刑罰、平和と秩序、キリスト教の普及などの概念から明らかにしようとしている。2014/08/02
-

- 洋書
- MÃ(c)dÃ(c…