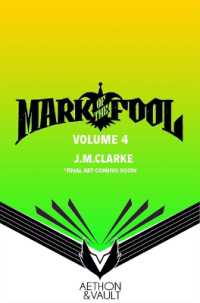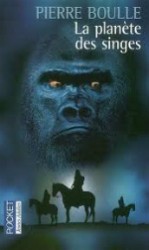感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マッピー
15
20年以上も前に読みたい本リストに載せた本なので、今更少年期の心を知ったところで…という気もしないではなかったけれど、書かれたのはさらにもっと前で、学生時代に精神分析とか心理学の本を読み漁っていたころの空気を感じる内容だった。たぶん自分の子どものことを念頭においてこの本を読もうと思ったと思うのだけど、実際には自分の子供時代のことが次々思い出されて、実は私は結構危ういところにいたのではないかと思った。3歳から5歳くらいの思い出はいくつもないけれど、そのすべてが失敗体験だ。だから私は自己肯定感が低いのか。2024/08/07
れい
7
昭和の書であり、登場人物と筆者の会話からは、昭和の匂いがする。ニックネームはなかなかユニークな名付け方だと感じた。言葉を用いていても、イメージの世界を共有することで、彼らとの距離をぐっと縮めている気がした。2018/07/29
坂口衣美(エミ)
5
少年期のこどもたちの精神療法が専門用語が少なく、やさしい語りで書かれている。読みやすくて心に響く。1987年初版なのでやや古めかしいところもあるが、良い本だと思う。子供時代というのは重要な基礎になる部分なのだな…と思うたびに、自分は「まっとうな」子供時代を過ごしたのだろうかと不安になる。2015/02/03
alto弾き
2
1978年初版の本なのに、登場する少年たちの不登校や緘黙、身体症状とその要因は、今と少しも変わらないように思えた。「少年たちの神経症をみていると、その大部分は少年たち自身の問題というよりは、周囲の環境に影響されたもので、いわば自我が弱い立場の子どもが一番最初に『犠牲の山羊』として選ばれる」。子供たちの「問題行動」は彼らのできる限りの「表現」である。山中先生自身が少年の心を持ち、いきいきとした心で子供と関わり合う。子供たちと山中先生の人間同士の真の交流に、自分のなかの「少年期の心」が心の奥底から顔を出した。2025/12/17
る-さん
2
どの症例も興味深かったが、特に印象に残ったのは子と親の治療を一手に引き受けていたことで現れた両面怪獣から、どっちつかずで曖昧な治療者の態度が原因だと見立て、親の治療を別途依頼し子に専従することで効果が表れてきたこと。『解釈』という行為が本当に難しそうだと感じたが、実質治療者を安心させるためのもので、その是非より安定した態度が患者にとって最も大切なものだと知って安堵した。子どもの態度が家庭の問題を物語るというのは親には耳が痛い話だが、現実の両親像と子どもからみたそれは違う、ということを念頭に置いておきたい。2023/07/15