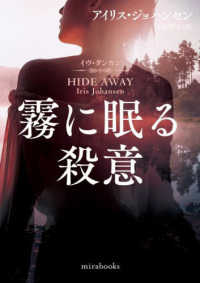感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
saga
51
山城から城下町への変遷、輸出入における金銀の海外流出、幕府役人の贈収賄事情など、興味深い話題を扱っているが、中でも農業・農民に関する項目が興味深かった。江戸時代は米を中心とした石高制であり、それを支えたのが農民だ。100万都市と言われた江戸の人口を支えたのも農業の発展である。しかし、新田開発を推し進めた結果、本来の耕作地は人手不足で荒廃し、大規模な災害が発生したことから、幕府は諸国山川掟で水源となる森林開発を抑制した。現代でも開発に伴う災害が発生するが、江戸の失敗事例が生かされていないことに愕然とした。2024/07/21
ジュンジュン
13
通史ではない。江戸時代を特徴づける現象を選び、それを以って江戸時代の流れと意義を考察する。初期の大開拓時代、城下町の成立、100万都市の実態、絹と金銀の関係など。一番へぇ~だったのは、問:明治維新で得をした者は?→「領主階級は維新変革による被害者ではなく利得者である」(242p)。なるほど、明治維新を江戸時代から眺めるとそうなるのか。2022/05/23
mackane
13
日本の近世にあたる江戸時代。中世より続く商業基盤や金銀鉱山開発によって力を蓄えた諸大名による戦乱後、徳川が天下を握るとその経済力を背景に、長期の安定が続いた。治水土木技術が向上し大規模な平野開発が可能となり、古代より支配者が目指していた農本主義も完成、都市人口も激増。自然由来ではない計画的な都市設計も進む。身分も固定化された。鎖国という名の対外「開国」政策を行い、貿易量を増加させつつも価値観や地方勢力増強を制御した。しかし、最後は、多くの藩が財政破綻し資金繰りに困窮、外国からの圧力の中、終焉を迎える。2014/04/06
fseigojp
11
江戸時代を前期と後期に分ける 前期は大開拓時代 いまの県庁所在地のほとんどはこのころが発祥 18世紀以後は人口も頭打ち 18世紀に日本に外資がこなかったのは謎2021/03/06
珈琲好き
10
江戸時代は大新田開発時代。江戸時代(1867年)以前の大規模治水の3割強が江戸時初頭に集中してるのは、大規模河川を一円支配できる権力が確立したのが古代以来だったため。平安から室町までの耕地面積はほぼ変わらないが、室町から江戸時代中期(1720年)には3倍になっている。/新田開発が進みすぎたため早くも1650年頃から洪水が多発するようになる。そのメカニズムは、田畑や肥料採取のために山を丸裸にする→土砂崩れが起きる→河川の河床が高くなり洪水が起きるというもの。2018/01/31
-
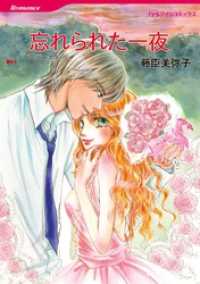
- 電子書籍
- 忘れられた一夜【分冊】 5巻 ハーレク…
-

- 和書
- 聖なるものの精神分析